|
彼女にとって、誕生日は特別だった。 一つ年を取る度に、また一つ彼から遠ざかった。 最近になって、ようやく彼女は気付いた。 本当の恋は、憧れて背伸びして無理矢理に引き寄せようとするものではないのだと。 そっと隣に寄り添い、空気のようにさりげない存在なのだと。 だから、切なかった。 年を取ることも、背が伸びることも。 決して戻らない日々の、記憶を辿ることも。 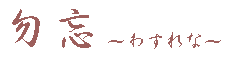 暖かい春の日。エーコはリンドブルム城の自分の部屋にいた。 大きな窓の下に据え置いた机に向かい、彼女は一心に何かを書き綴っていた。 白い羽の柄の付いた細身のペンは、もう十年近くも、彼女の想いを綴り続けていた。 学校の宿題、日記、手紙。 時には、母親から聞いた料理のレシピをメモすることもある。 しかし、今彼女が書いているのは、彼女が六歳の時に起こったあの出来事―――ガイアの全てが巻き込まれた、あの戦いについてだった。 もっとも、幼子だった彼女には忘れてしまっていることの方が多かった。 それは、仲間たちと当時の話をする度に思うことだった。 そんなことあっただろうか? と、必死に記憶を辿ってみても、結局思い出せない。 その度に、消えていく記憶が切なかった。 忘れていってしまうことが申し訳なかった。 それとも、彼は微笑って言うのだろうか? もう、忘れてもいいんだよ。 一緒に戦ったって事実は、消えて無くなりはしないから―――と。 エーコは手を休め、窓の外の空を見た。 イーファの霧が晴れた日の、あの青空を忘れられない。 初めてアレクサンドリアへ行った日の、あの驚きを忘れられない。 彼の、戦う決意を知った日を忘れられない。 彼が死んでしまった日を、忘れることができない。 子供ならではの時間の流れは、コントラストをつけたように部分部分の記憶を引き立たせた。 だから、他の誰が忘れてしまっても、彼女だけは忘れられなかった。 小さな命の光が消えた、その瞬間を。 コトリ、と、エーコはペンを置いた。 いつもいつも、同じところを堂々巡り。 何度書いても、何度思い出しても、いつも目の前には金色の瞳と優しい微笑みばかりが浮かぶ。 ―――忘れることなんて、出来ないわ。 あたしにとって、あなたは今でも特別なお友達だから。 彼女は紙の端に、小さな絵を描いた。 小麦の穂で編んだ、小さなとんがり帽子の絵を。  -Fin-
back. |