朝焼けの光が、縺れた巻き毛の先を照らした。
昨日までそこに在ったものがなくなっていた。高くそびえるアレクサンドリアの聖剣、賑やかな人々の声、清々しい朝の空気。
ベアトリクスは、剣を握ったまま固まってしまっていた指を、無理矢理開いた。ギシギシと音でもしそうなそこから、セイブザクイーンが滑り落ちる。
終わってしまった、何もかも。
剣は、その名に反して女王を守りはしなかったのだ。
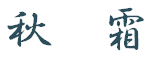
1802年、アレクサンドリア。
窓の外には、赤いレンガの美しい街並みが広がっていた。
王都アレクサンドリア。聖剣と湖の国。
ベアトリクスは、街がその全てを取り戻した風景を眺めた。
活気、賑わい、笑い声。あの夜失われた魂たちは戻りはしなかったが、街は着実に美しさを取り戻し、人々は生活と希望を取り戻し始めていた。
全てを失ったアレクサンドリアの民が全てを取り戻すその日まで、決して自分の罪に屈してはならないと心に誓い、今日までやってきた。
例え冷酷だと罵られたとしても、無情だと非難されるのだとしても、胸に沸き起こるざわめきを必死に押さえ、ただただ街と、そこに住む人々の傷を癒すことだけを考えた。
アレクサンドリアを滅ぼそうとした存在を憎いと思った日々。しかし、思えば思うほど、ならばブルメシアを滅ぼした自分は何なのかと、問わずにいられなかった自分。
ベアトリクスは、自分の両手を見た。
血と、罪と、人々の恨みに濡れた手。
奪ったものはあまりにも多いのに、守ったものは一つもないのだ。
セイブザクイーンを、腰から抜く。
ブルメシアがアレクサンドリアを許すとしたら、それは私の居ないアレクサンドリアでしか有り得ない。
この手が奪い続けてきた魂たちが安らぎを得るとしたら、それは私が安穏の日々を送っていては有り得ない。
さようなら。
私は、幸せになってはいけないのです。
***
スタイナーは城の中をうろうろと歩き回っていた。
さっきまでそこに居たベアトリクスの姿が見えないのだ。
あの戦いが終わり、城に戻り、ベアトリクスと共に女王を支え続けてきた。アレクサンドリアの破壊され尽くした街並みを取り戻し、人々の生活を戻すのは、苦労も多く、大変な仕事だった。だからこそ互いに助け合うことが必要だったし、いつしかそれは当たり前のことになっていた。
それなのに、彼はどこかで、いつか彼女を失うのではないかと、そればかりを恐れていた。
いつか―――そう、何もかもが元の通りに戻り、これでもう大丈夫とほっと安心したその瞬間、その次には彼女を失っているのではないか。
スタイナーにはそれを言葉にするのは難しかったが、言葉に出来ないが故、自分の身を省みることもせずに猛烈に働く彼女に不安は募った。
相変わらずうろうろと歩き回っていると、女王の部屋のドアが開いていたので、スタイナーは通りすがりにちらりと覗いた。
ガーネットがテーブルの前に突っ立って、じっと何かを見ていた。
どことなく尋常ではなかった。
「姫さま」
呼びかけてみると、女王ははっとしたように振り向いた。
「スタイナー!」
彼女は叫び声を上げた。
「ああ、スタイナー、どうしましょう」
「何がどうしたのでありますか」
一礼して、部屋へ入ってみる。テーブルの上には、ベアトリクスの愛剣がぽつんと置かれていた。主を失ったそれが、夕日の光を跳ね返してスタイナーは瞬きした。
「ベアトリクスは、アレクサンドリアを出て行くつもりだわ」
ガーネットもセイブザクイーンを見つめながら、今度は低い声で言った。
「何と?」
「剣を置いていくなんて、一体どこへ行くつもりなのかしら……」
忠誠を誓った聖騎士剣。
彼女の魂そのもののような、剣。
「まさか……あやつは」
スタイナーが呟いた。ガーネットが見上げる。
魂を失った騎士が、生きてゆけるはずがない。
「スタイナー……?」
彼の主は、訝しげな表情をしてその名を呼んだ。
しかし、それに答えることもなく、スタイナーは踵を返して部屋を飛び出していった。
ガーネットは吃驚したようにその背中を見送り、やがて小さく頷いた。
そうだったのか。彼と、彼女は―――
***
「待て、ベアトリクス! どこへ行くのだ?」
呼び止められ、ベアトリクスは歩を止めた。まさか彼がそこにいるとは思わなかったため、常になくびくりと竦んでしまった。
「どうか理由は聞かないでください」
背を向けたまま、ベアトリクスは搾り出すように呟いた。しかし、スタイナーは引き下がってはくれなかった。
「理由などを聞きたいのではない!」
小さく、震える。
どうしても、彼の目を見てはいけなかった。あの目を見てしまったら、きっと決心は揺らぐだろう。
莫迦な女だ。どれだけたくさんの幸せを踏みにじってきたことか。その上で、自分の幸せを望もうなど。
スタイナーはしばらく何かを口ごもっていたが、やがて、きっぱりとこう言った。
「自分は、もう二度とおまえを失いたくないのだ!!」
ベアトリクスは思わず振り向いてしまった。
彼が自分のことをそんな風に言ってくれるとは、思ってもみなかった。胸の中に、どこかから喜びと悲しみが同時に染み込んできた。
「スタイナー……」
「これからも一緒にガーネット女王をお守りして欲しいのである!」
ベアトリクスにはわかっていた。それは、彼なりの愛の告白であること。あの―――忌わしい夜、別れ際に言い募ろうとしたのは。
一度だけ、彼に温もりを与えることを許してもらえますか。
彼には、罪はないのです。
ベアトリクスはスタイナーの元へ走り寄った。哀しくて、涙が零れた。
「ごめんなさい、スタイナー。私は行かなければならないの」
奪うことしか知らない手は、あなたに触れたがって疼くのに。
これ以上何も奪いたくはないから、差し伸ばしてはならないのだと引き留める。
「何故であるか」
「私の罪は深いのです。最早償えないほどに深いのです」
「そんなことを……。一体どこへ行って、どうするつもりなのだ」
―――どうしようかなど、考えていなかった。
黙ってしまったベアトリクスの顔を覗き込みながら、スタイナーは小さく問い質した。
「その……死ぬつもりだったのでは、あるまいな?」
丸腰で街を出れば、モンスターの餌食になっても文句は言えないだろう。結果論から言えば、それは然りということになったに違いなかった。
「ベアトリクス」
スタイナーは窘めるような声色になった。グローブを外すと、まるで壊れ物にでも触れるかのように緊張した指先で、彼女の頬に触れた。滑らかなそこには、夕日を反射させたまま、涙が零れ続けていた。
「それで、おまえは楽な道を選ぶのであるか。そのように弱い心の持ち主であったとは、がっかりしたのである」
涙を拭い続けながら、スタイナーはそう言った。
「え……?」
ベアトリクスは驚きの籠もった声で返した。
「確かに、この世から消えてしまえば、もう罵倒の声も聞こえないであろうし、罪の意識に苦しむこともないであろうが」
目を見開いて見つめてくる鳶色の隻眼が、いつからこんなに哀切の色を湛えていたのか、スタイナーにはわからなかった。
あれからずっと、彼女は独り、罪を背負って生きてきたのだ。
「それは、戦うこともせず、背を向けて逃げることと同じである」
スタイナーは言葉を続けた。
「生きて許しを乞うことは、簡単なことではない。時には屈辱さえ覚えることである。しかし、それこそが棘の道。どんなに困難ではあっても、逃げることなく、背くことなく、戦うべきなのである」
ベアトリクスの瞳に苦悶の影が射し、不安になったスタイナーは次第に声の調子を落として、最後にはこう付け加えた。
「……と、自分は思うのである」
「そういうことではないのです」
ベアトリクスは哀しそうに言った。
「許されようなどと、虫のいいことは思っていません、スタイナー」
小さく頭を振り、ベアトリクスは否定の色を強めた。
「私はただもう、奪いすぎるだけ奪ってきたのです。そんな私が、一体どうして幸せを手に入れようなどと……そんなことを考えるなんて、あってはならないことですわ」
「そうであろうか」
スタイナーは呟いた。
「確かに、奪ってきたものは多いかもしれんが、それとこれとは関係ないように思うのであるが」
再びベアトリクスは吃驚したように彼を見上げた。
「何てことを! 関係ないわけがありません」
「ベアトリクス、おまえが不幸にしていて、おまえが奪ったものは戻ってくるのであるか?」
「……いいえ」
それは、ベアトリクスにもわかっていた。失われた命は永遠に戻らない。ベアトリクスには、痛いほどによくわかっていた。
「おまえが奪ったものたちは、おまえの不幸を喜ぶとでも思うのであるか?」
「それは……」
「それこそ、虫のいい話ではないか、ベアトリクス。自分が不幸になれば、それで許されるような気になっているだけなのではないのか?」
彼女ははっとして、目を瞠った。そのまま、彼女の瞳から再び涙が溢れ出す。
涙は後から後から溢れ、スタイナーは知らぬ間に酷いことを言っていると気付いて、些か慌て出した。
「あ……いや、その……自分はおまえを責めているわけでは……」
「いいえ、あなたの仰るとおりですわ、スタイナー」
ベアトリクスは絶望した声で言った。
「私は、自己満足のために不幸を選ぼうとしていました。でも、その結果は、ただ自分のため……自分で自分を許したいと願っているだけの、莫迦な振る舞いでした」
幸も不幸も選ぶことの出来ない、哀しい運命。
ベアトリクスは、それが自分に与えられた罰なのだと悟った。なんて、残酷な罰なのかと。八つ裂きにされた方がどれだけましだろうか。
「ベアトリクス……」
こんな時、どうすればいいのかスタイナーは知らなかった。涙を拭ってやるためのハンカチなど持っていなかったし、気の利いた言葉を掛けて慰める術も持っていなかった。
どうしたら引き止められるのか、そのことばかりを考えていて、余計に傷を深くしたらしいことをスタイナーは認めざるを得なかった。自分の不器用さを、これ程までに呪ったことはない。
「私はアレクサンドリアに留まります、スタイナー。生きて罪を償います」
言葉だけなら大変に前向きな決心だったが、その表情はあまりに痛ましかった。
「ならば、自分と一緒に姫さまを支えてくれるのだな?」
彼女の出した答えはわかっていたけれど、スタイナーは訊かずにはおれなかった。
「いいえ」
ベアトリクスは、やはり否定した。
「汚れたこの手で、これ以上ガーネット様のお傍に居るわけには参りません」
あの剣を、握るわけには。
「ガーネット様のことは、スタイナー、どうかあなたがお守り申し上げてください」
―――身勝手ばかりを言って、申し訳ありません。
ベアトリクスは最後にそう言って、頭を下げた。
スタイナーは何か言おうとしたが、何も言えなかった。
***
「こんなものは受け取れないわ」
ガーネットは執務机の上に差し出された封筒を押し戻した。
「ベアトリクス、退役するなんて私は許可できません」
「どうかお許し下さい、ガーネット様」
押し戻された封筒を、もう一度押し返す。封筒は真っ白で、表書きに「退役志願書」と書かれていた。
「どうして辞めようなんて考えるの? ブルメシアのことがあったから?」
ガーネットは立ち上がり、封筒を掴むと、ベアトリクスの手の中へ戻した。
「ブルメシアのことは、あなた一人の問題ではないのよ。アレクサンドリアの国全体の問題だわ。あなた一人が個人的に解決できるようなことではないし……」
「わかっております」
ベアトリクスは静かに答えた。ガーネットはしばらくの間彼女を見つめていたが、一瞬だけスタイナーを見た。彼は居た堪れない顔をして、ドアの側に立っていた。
「兎に角、あなたが辞めてしまったら私が困るもの。これは受け取れません」
「ガーネット様、後生ですから……」
「ベアトリクス」
毅然とした声で呼ばれ、ベアトリクスは小さく息を吸い込み、口を閉じた。
「あなたはきっと、罪の意識に駆られているのでしょう? たくさんの人々の命や生活を奪ったことに」
ガーネットは背を向け、窓の外を眺めた。秋の空はどうしてこんなに青いのだろう。いっそ、疎ましいほどの青さだった。
「そのことに関しては、あなたがそれを罪と感じるのと同じくらい、私にも罪があるのよ」
「とんでもございません、ガーネット様。お止めになろうとしたのは、ガーネット様です」
「いいえ」
彼女は頭を振り、振り向いた。
「お母さまが為さったことだもの。女王の位を継いだということは、そういった罪や、責任や、全てを継いだのと同じことだと思うのよ」
ガーネットは、ベアトリクスの両手に触れた。一瞬手を引こうとした彼女を、女王は許さなかった。
「あなたがこの両手で抱え続けている痛みは、あなた一人のものではないわ。だから、このままずっと側にいて、私と一緒に償いましょう、ベアトリクス」
「ガーネット様……」
「ごめんなさい。お母さまがあなたにしたことを、簡単に許してくれる気にはならないでしょうけれど―――あなたを苦しめるような命令を出し続けたこと、心から謝ります」
ベアトリクスは信じられないものを見るように、女王を見つめた。彼女が自分に謝罪の言葉を述べるなど、あってはならないことだった。
「ガーネット様!」
「さっきも言ったでしょう? 全ては私が継いだのよ」
そう言うと、女王は悲しげに微笑んだ。
「さぁ、ベアトリクス。そんなものは仕舞って、剣はそこにあるわ」
しかしベアトリクスは、暖炉の側に立て掛けてあったセイブザクイーンを一瞥した後、頭を垂れた。
「申し訳ありません。あの剣だけは、もう私には持つ資格はありません」
「どうして?」
ガーネットは驚いてベアトリクスを見た。
「私は、守ることが出来ませんでした―――ブラネ様も、ガーネット様も」
そんなことはないわ、そう言いかけて、ガーネットは止めた。どんなことを言っても、彼女の心が変わりそうにないことを見抜いたのだ。
あの剣は、今の彼女には重過ぎるかもしれない。
「あなたはそれでいいの? あの剣を手放してしまって」
「致し方ありません。私に、選択の余地はないのです」
「そう……」
ガーネットは少しの間、黙って何かを考えていた。もう一度、一瞬だけスタイナーを見る。彼はベアトリクスの背中を、心配そうに見つめていた。
「わかったわ」
ガーネットは頷いた。
「その代わり、賭けをしましょう」
「賭け……ですか?」
ベアトリクスは心底驚いたように呟いた。
「もしも―――」
何を、賭けようか。ガーネットはぐるりと思い巡らせた。
「もしも、あの人が―――ジタンが無事に帰ってきたら」
ガーネットの口唇からは、何故か彼の名が滑り出ていた。
「その時は、もう一度あの剣を握って頂戴、ベアトリクス」
賭けを提示された相手は、目を丸くして女王を見つめていた。
「何故、ジタン殿が……」
ベアトリクスの問い掛けに、少しだけ俯いて、
「私が抱えている、一番重い罪だから」
ガーネットが呟くと、聞こえなかったのか、スタイナーが身じろぎした。
「一緒に、あの人が帰ってきてくれることを願ってくれる?」
それは同時に、再びあの剣を握りたいと願うことだった。ベアトリクスは言葉もなく、ただただ女王を見つめていた。
「ベアトリクス?」
「……わかりました。ガーネット様とご一緒に、お祈りいたします」
「ありがとう」
ガーネットはセイブザクイーンの側まで行くと、手に取って、スタイナーのところへ歩み寄った。
「それまではスタイナー、あなたがこの剣を預かってくれるかしら」
スタイナーは幾分呆然としていたが、はっと我に返ると、彼の敬愛する女主から剣を受け取り、恭しく頭を下げた。
ガーネットは、もう一度哀しげに微笑んだ。
***
しかし、再びあの剣を手にする日が来ようとは、ベアトリクスには実は考えも及ばぬことだったのだ。
あの日と同じように劇場艇がアレクサンドリアへやって来たのは、あの日と同じような夕暮れ時の、赤く美しい時間だった。
あの日と同じ劇団が同じ劇をし、ただ違うのは、あの人物がそこにいないことと、彼女の腰にあの剣が差されていないことだけのようだった。
最も、今日は女王の旧友たちが一堂に会していたし、演劇好きの前女王はもうその席に座ることは出来なかった。
それでも、ベアトリクスにはジタンがその場にいないことこそが、あの日と今日の最も大きな違いであると思えた。
しかし、本当はそうではなかったのだ―――
その瞬間。駆け出した女王のために、スタイナーとベアトリクスは扉を開け放つ。
女王が去っていったテラスから、ざわめく客席を見ようとベアトリクスは身を乗り出した。
ちょうど女王が客席を飛び出し、長い間待ち続けた恋人の胸に飛び込んだのが見えた。
夢のようだとベアトリクスは思った。
まるで運命に引き寄せられたかのように、彼らは再び廻り逢ったのだ。
「ベアトリクス」
スタイナーに後ろから肩を抱き寄せられ、ベアトリクスは振り向いた。自分の口元が綻び、いつにないくらい微笑んでいたことに、今更ながら気付く。
スタイナーは何も言わず、剣を取り上げた。刀身が夕日の光を跳ね返して、ベアトリクスは一度だけ瞬きする。
彼はベアトリクスの手を取ると、その剣―――セイブザクイーンを握らせた。
もし。
もしまた、この剣を握る時が来たら。
その時は、ベアトリクス。約束してはくれまいか。
ベアトリクスの手を自分の手で包むと、スタイナーは彼女の手ごと、君主に向けて剣を掲げた。
もう一度、女王陛下をお守りするという任務を、自分と共に果たすと。
ベアトリクスは笑った。どうして笑ったのか、後から考えても思い出せなかった。ただ、ずっと心を覆い続けていた闇が破れて光が射し込んできて、まるでどちらの方向へ行けばいいのかを思い出した迷い子のように、ベアトリクスは笑った。
「ベアトリクス」
二人の手によって掲げられたセイブザクイーンは、彼らの最も敬愛する女王の元を照らしていた。
たくさんの祝福と歓迎を受けながら、今この世で最も幸せな二人を。
スタイナーが何事かを呟いた。
きらりと、剣が煌く。
ベアトリクスは、歓声に掻き消されて聞こえなかった言葉を、もう一度と促した。
 > >
-Fin-
3年目終了時から、来年はスタベアですね!と言っていたので、
今年は季節が近づくにつれて自分の中でも一気にスタベアモードになっていっていた感があります。
そして、11月26日は任務の日。彼らのどの部分を舞台化するか(せいちゃんの物語はまさしくそんな言葉が相応しいと!)
即刻決まったのでありました。せいちゃん、じっくりことこと煮込むようにスタベアの軌跡を辿らせてくださり本当にありがとう!(歓喜)
今回の舞台はアレクサンドリア。2002年のオレンジとは別の意味合いを持つ夕焼けの色を思い浮かべながら読みました。
ひとつひとつを綺麗に丁寧に重ねていくスタイナーとベアトリクスのシーンは読み手の気持ちをじりじりと暖めてくれました。
遠まわしにしない、はっきりとしたやり取りは決して冷たいものではなく、
そこに愛がある、ということを確実に教えてくれたように思います。
スタベア絵・・・。描くのは初めてだったのですが、とにかくスタイナーをベアトリクスさんに合わせてリアル化するのが
とーっても難しくて、スケッチブックをぼそぼそにしてしまいました(笑)ごめん、スタイナー・・。
でもたのしーくたのしーく描かせていただきました。もちろんBGMはその扉の向こうに(んもういい曲!)
そうか、もう4年目だったのですね。FF9の発売の一年後から始まったこのE-flow、今年も本当に有難うございました。
さーて、お次は!?笑
2005.11.26 リュート
こうして二人でお誕生日をお祝いし合うのも4回目。今回も、りゅーちゃんに心いっぱいのありがとうです!
何と言っても、今回初めて完全に未完成の作品のまま、途中までしか書けていない状態でとりあえずお送りしてしまい、
こんなんなっちゃってどうしましょう、とか泣き言を入れつつ、りゅーちゃんの応援の言葉を戴きながら、
なんとか完成に漕ぎ着けました(^^;) 励ましと優しさをしみじみと、ありがたく噛み締めながらの執筆でした。。
りゅーちゃん、未完成でズルズル長い私の小説を根気強く読んで下さって、完成まで付き合ってくれて本当にありがとう(涙)
そしてそして、リアルVer.スタベア・・・v EDのシーンを彷彿とさせる構図と言い、ベア様の微笑みと言い、
小さく題名を説明して下さってる端っこといい(笑)、愛を感じますvv
スタイナーがリアルになったらこんな風なのですね・・・カッコいい(笑) うわ〜、何だかドキドキしてきちゃいました!
今回、イラストを入れづらい感じの話になっちゃったかな、と密かに思っていたのですが、
爽やかにさらりと描いて下さって、さすがはりゅーちゃん! と改めて感動してしまいました。
素敵なセイブザクイーン、嬉しいです♪
また来年も、楽しくドキドキとお祝いできたら嬉しいです。来年はついに5年目に突入ですか・・・!
お互いの幸せな1年を祈りつつ。。ありがとうございました♪
2005.11.26 せい
|
back.
| 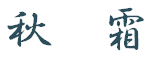
 >
>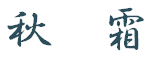
 >
>