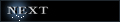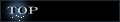|
<2>
夢を見た。
寝覚めの悪い夢。
目が覚めたら記憶は全て消えて、ただ後味の悪さだけが残った。そんな夢。
ダイアンは寝台から降り立ち、窓から夜空に二つの月が寄り添うのを見上げた。
両親が亡くなって、十年。
この星は、日ごと夜ごとに荒々しさを増し続けている。
ダイアンは、この惨状を両親が見ずに済んだことを幸いと思った。
誰よりも、ガイアを愛した人たちだったから。
あるいは、初めから見るはずもなかったのかもしれない、けれど。
ある種の予感は、常に彼の心の中に存在していた。
父と母の生はガイアを救い、
そしてまた、彼らの死がガイアを陥れた。
もしそうだとしたら、この星はもう二度と救われることはないのかもしれない。
ダイアンは自分の思考に自分で頭を振り、もう一度寝台へ戻った。
こんな風に夜がゆっくり過ぎていくのをただじっと待っているしかない自分に。
まるで成長していない自分に、嫌気が差した。
***
「王子、次の討伐が決まりましたよ」
と、彼の義兄はそう言って笑った。
この人はこんな風に疲れた笑みを浮かべる人だったろうかと、ダイアンはそんなことを一瞬思った。
「冬越えになりそうだね」
「ええ」
「今のうちに兵たちを休ませておかなければな」
ダイアンが呟くと、ウィリアムも頷いた。
「それから、息子の初陣も決まりました」
付け加えるような義兄の言葉に、ダイアンは思わず目を見開いた。
「ウィル、まだ早いよ。あの子はまだ十五だろう?」
「行くと言って聞かないもので」
「駄目だ。僕が言う」
そうしてくれと、ウィリアムの茶色い瞳が悲しそうに訴えた。どうしても父親の言うことを聞かないらしい。
「姉上は?」
「行かせると言っています」
溜め息を一つ。兵の犠牲が増える度に、女王が厳しい立場に追いやられていることは知っていたけれど。
ルイスは、まだたったの十五歳だ。早すぎる。
それに、今度のはいけない。
嫌な予感がする。
わざわざ、そんな時に初陣をさせるわけにはいかない。
それは、ある種の予感だった。今度の討伐隊は、たぶん無事に帰ってはこられないような予感がした。
忘れられた大陸に湧き出るモンスターはますます脅威を増していたし、兵士たちの疲弊は年を追うごとに大きく重くなっていた。
終わりのない戦い。永遠に続く戦い。人々は疲れ切って、もう二度と未来への希望なんて抱けないと思っている。
荒廃への道を進み続けるガイア。
ダイアンには、堪らなく何もかもを投げ出したいと思う時があった。
全てを投げ出して、逃げてしまいたいと。
そして恐らくそれは、彼だけのことに限ったものではないのだ。
甥っ子は、頑ななまでにどうしても行くと言って聞かなかった。
この子は、死にに逝くのだとわかって言っているのだろうか。
ダイアンにも、ついにその少年を説得できなかった。
彼が初めて戦場へ行った時、彼の母がそれを止めることができなかったのと、同じだった。
***
「今度の戦は長引きそうなのですか?」
ダイアンの荷造りを手伝いながら、ステラが寂しそうに尋ねた。
「ああ、たぶんね」
この荷造りも、戦になる度に繰り返されてきた、一種儀式のようなものだった。
「いつお帰りになるとしても」
真新しいタオルを畳みながら、ステラは穏やかな口調で続けた。それも、一種の儀式だった。
「私は、ずっとこのお城でお待ちしており」
「ステラ」
それが、遮られたのは初めてだった。吃驚した彼女は、手を止めて顔を上げた。
「駄目だ。もう待ってはいけない」
「嫌ですわ」
「駄目だ」
いつもと違った。いつも「待たなくていい」と言って出掛けたけれど、待ってはいけないと言われたことなんて一度もなかった。
ステラの胸に、言いようのない不安が広がった。
「ダイアン様……」
「僕が発ったら、君は城を下りて結婚するんだ」
「嫌ですわ!」
「駄目だ、そうするんだ。命令だ」
「できません!」
ステラは思わず金切り声で叫んだ。
「私がお待ちしていれば、ダイアン様はいつもご無事で戻ってくださるでしょう? 願掛けですわ!」
「いいや、駄目だ」
「ダイアン様! どうしていつもと違うことを仰るの?」
今や、ステラにもダイアンが何を考えているかはっきりとわかった。
「いけませんわ! どうかご無事でお戻りを……!」
「約束できない」
ダイアンは顔を背けたまま、素っ気のない口ぶりでそう言った。
ステラの唇から啜り泣きが漏れる。
「―――もう、戻れないかもしれないんだ」
小さな声で、彼はそう付け加えた。
「今度こそ、本当に戻れないかもしれない。だから、君はもう待つと言ってはいけない」
待つと言われたら、待たせなければならない。
そして、待たせたまま逝かねばならない。
「待ちます」
「駄目だ」
「いいえ、待ちます」
ステラは気丈に泣いた。
本当に、この城の女たちはみな気丈に泣くのだと、ダイアンはそう思った。
―――どうして、みな不幸の道を選ぶのだろう、と。
「私は、永遠にあなた様をお待ちします」
それから、まるで小さな罪を告げるかのように、お慕いしております―――と、彼女はそう言った。
言ってしまった。
この、若く不幸な人を待たせてはいけない。
わかっていたのに、彼には押し留めることができなかった。
それはまるで、何ものかに導かれたような秘め事だった。
声を殺して泣き続けるのを、腕に抱き取って閉じ込めたまま。
抱き続けた想いは、ついに、踏んではいけない轍を踏んだ。
初めて、王子は「待っていて」と言ってアレクサンドリアを発った。
彼の率いる討伐隊は冬越えになる……はずだった、のだが―――
|