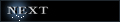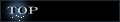|
<3>
***
ダイアンは目の前の光景を見つめていた。
自分はもう死んだのか、それともまだ生きているのか、それさえも彼にはわからなかった。
体はもう、指の先さえ動かすことはできなかった。瞬きもできなかった。
だから、見たくはないそれらからも、目を逸らすことはできなかったのだ。
風に混じる鉄錆の臭いと、累々と続く屍たちだけが、今の彼が認識できる全てだった。
その直前まで、そこに活き活きと動き、呼吸し、こんな地の果てでも何がしかの希望を絶やさずにいた、そんな人たちが。
今は誰も何も言わない。ただ吹きすさぶ砂埃の下で、まるで無機質なまでに。
すぐ側で倒れたまま動かない茶色の頭から、一房の巻き毛が土の上に縺れているのを見た時、ダイアンは激しく後悔した。
助けられなかった。
まだ、たった十五だったのに。
―――全て、僕のせいだ。
僕が最初から戦へなど行かなければ。前例など作らなければ。
この子は戦場などへ借り出されずに済んだ。死なずに済んだのだ。
僕は君に、一番残酷なことをしてしまった。
許しを請うことさえ、できないようなことを。
この子の母は失望する。
激しく、失望するに違いない。
どうか自棄しないでほしい。ダイアンはそう祈った。
全ては、全ての罪は、この身に受けて逝きますから。だから姉上、どうか……
ダイアン・フェイル・アレクサンドロスがその最期に想ったのは、彼の手で不遇な罪を背負わせてしまったその人への、懺悔の言葉だった。
すまない、ステラ―――
*
それでも崩れ落ちなかったのは、彼女が女王だったからだ。
ウィリアムとダイアンが率いる軍勢と連絡が取れなくなった、と報告があった時、或いはもう覚悟を決めていたのかもしれない。
それでも、覚悟を決めるのと、実際それを聞くのとでは、雲泥の差があった。
「初めにルイス様がモンスターの軍団に不意に斬り込まれて、それをダイアン様がお庇いになられたそうで……士気が乱れ、退軍が間に合わなかったとのことでした」
「―――全軍ですか」
まるで自分の声ではないような声で、エメラルドはそう呟いた。
聞くまでもなく、彼らの隊が壊滅的な被害を受けたことは、想像して余りあった。
「……絶望的だろうと」
「わかりました。とにかく、他の隊は全て退陣してください。これ以上の被害は国の存亡に関わります」
御意を受け、連絡係の兵士は女王の間を駆け出していった。
「お母さま」
どれくらいそうしていたのだろう、椅子に凭れたまま、エメラルドは動けなかった。
「お母さま」
小さな声で呼ばれ、ようやく顔を上げる。
「どう、なさったの?」
真夜中はとうに過ぎていた。小さな姫君が目を覚ましているような時間ではなかった。
異変を感じて起き出してきたのだろう。
「ガーネット」
腕を引き寄せて、小さな体を抱きしめた。
「みんな……みんな逝ってしまったのよ」
ガーネットはじっと抱かれたまま、黙っていた。
「お父さまも、お兄さまも、叔父さまも、みんな逝ってしまったの」
どこへ? とも、どうして? とも尋ねなかった。
幼子は、ただ震える母の腕に黙って抱かれているだけだった。
|