|
「ねぇ、ジェフリーの初恋っていつ?」
という突拍子もない問い掛けに、ジェフリーは思わず「はぁ?」と返してしまった。
「初恋?」
「うん、初恋」
青い目はキラキラ輝いている。手元を覗くと、リアナか誰かから借りたのだろう、女の子向けの小説があった。
「何歳の時だった?」
「え? ……えーっと」
サファイアがあまり熱心に尋ねるので、ジェフリーは古い記憶を掘り返してみた。
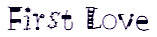
それは、エーコ公女の結婚式の日。
教会の脇の白くて美しいゲストハウスが気に入って、公女はそこで披露パーティをした。
呼ばれたのは彼女の仲間たちと、彼女の夫の仲間たち―――つまりはタンタラスの面々だった。
演芸室で『星に願いを』が始まると、ジェフリーはすっかり退屈になってしまって、仕方がないので屋敷の中を探検することにした。
こぢんまりとした屋敷だったけれど、普段タンタラスのアジトで雑魚寝同然の彼には、豪奢なお城のように見えた。
大きな窓から陽が降り注いでいるのを見て、ジェフリーはテラスから中庭に降りてみた。
そこには先客がいた。
小さな女の子。前向きに屈みこんでいるせいで、白いドレスのスカートからカボチャパンツが覗いていた。
そして、そこからふさふさと金色のシッポが生えて、揺れていた。
「何してるの?」
ジェフリーが声を掛けると、女の子はぴょこんと起き上がった。
「バッタ」
小さな指で芝生を指差す。
「バッタとってるの」
「こんな時期にバッタなんていないよ」
「いるよ」
ほら、ともう一度指差す。
ジェフリーは近付いて行って、足元を覗き込んだ。
確かに、緑色のやつが一匹、所在なさげに跳ねている。
女の子はまた屈み込んで、両手で掬って捕まえようとするけれど。バッタの方が些か俊敏だった。
それからしばらくの間、ジェフリーは女の子とバッタ捕りをした。と言っても、彼はただ見ているだけ。ジェフリーが捕ってやれば簡単だったのだけれど、女の子は頑としてそれを許さなかった。
バッタがぴょこんと跳ねると、カボチャパンツもぴょこんと跳ねてそれを追いかけ、さらにそれをジェフリーが追いかける、という妙な追いかけっこが続いた。
「ねぇ、もうやめようよ」
そろそろカボチャパンツを追いかけるのにも飽きてきた。たぶんバッタの方も飽き飽きしてきていることだろう。
女の子は顔を上げて、パチパチと目を瞬かせた。
「おうちに持って帰ろうと思ったのに」
ガッカリした顔をして、女の子は立ち上がった。
「家ってアレクサンドリアだろ? 寒いからすぐ死んじゃうよ」
「そうなの?」
ジェフリーは頷いた。もっとも、暖かい部屋の中で虫籠に入れておけば、しばらく生きるだろうとは思ったけれど。
バッタを諦めた女の子は、きょろきょろと辺りを見渡した。
「あれ、なぁに?」
と指差す。
「噴水のこと?」
「おもしろそう!」
ぴょこんと跳ね上がると、あっという間にそちらの方へ駆け出した。
ジェフリーも追いかける。どうせ暇だったということもあったし、噴水には興味があった。
追いつくと、女の子は手を伸ばして、吹き上げる水しぶきをつかまえっこしていた。
ヘリに膝をついて身を乗り出していたので、ジェフリーは落ちないようにとドレスのリボンを握り締めた。
思えば、いつも「小さなジェフリー」だった彼には、今までこんな風に年下の女の子の世話をする機会なんてなかったのだ。
どうやら世話を焼かれることだけは人並み以上だったから、どうすればいいのかを知っているらしかった。
「濡れちゃうよ」
ジェフリーは注意してみた。
「へーき!」
女の子はきゃあきゃあと歓声を上げる。
「濡れたら風邪引いちゃうよ?」
「へーき!」
教会の鐘が突然「ぼーん」と一度だけ鳴り、女の子は驚いたように空を見上げた。
「なぁに?」
「鐘が鳴ったんだよ。きっと芝居が終わったんだ」
急に興味が移ったらしい。女の子は噴水から降りて、じっと空を見ていた。
そして。
「サフィー、お屋根に登る!!」
「……えっ?」
ジェフリーがはっとした時には、もうテラスの白くて細い柱に両腕で抱きついていた。
「ちょ、ちょっと待って! 危ないよ」
「へーき!」
「平気じゃないったら!」
確かに彼女は身軽で、手足を使ってひょいひょいとかなりの高さまで登った。
しかし、半分くらいのところで突然止まった。
「どうしたの?」
「……疲れた」
「ええ!?」
両手を離そうとするので、ジェフリーは思わず大声で「離しちゃダメ!」と叫んでいた。びっくりするくらい、双子の姉そっくりの声が出た。
急いで後ろから登っていって、支えてやった。
「少し休んだら降りよう?」
「やだ」
「でも、落っこちたら怪我するよ? ドレスだって汚れるし」
既に真っ白なドレスはあちこち泥汚れがついていたけれど。
「お屋根登るんだもん」
女の子は頑なだった。
ジェフリーは困ってしまった。大人を呼んでくれば解決しそうだったけれど、場を離れた瞬間に下まで落っこちるかもしれなかった。汚れるくらいは何とかなりそうでも、怪我をしたら大変だ。
―――だって、彼女は小さな小さな王女さまなのだ。
「あのさ」
そこで、ジェフリーはいいことを思いついた。
「よそから来たから知らないだろうけど、屋根の上って魔物が住んでるんだよ」
「え?」
女の子は青い目を大きくした。
「子供が登ったら食べられちゃうんだ。もう2人やられたって友達が言ってた」
「……」
口をぽかんとさせたまま、女の子は何度か瞬きした。
そして。
「おもしろそう!」
目がキラキラする。
「サフィー、まもの見てみたい!」
「……え?」
「そしたら、おにいさまに自慢するの!」
「ちょ、ちょっと待って、食べられちゃうんだよ?」
「逃げるもん」
「逃げられないよ、すごく恐いんだよ?」
「恐くないもん」
さっきまで「疲れた」と言っていたのが嘘のように、女の子はするすると柱を登りだした。
「待っ―――」
「サフィー!」
突然、誰かが彼女を呼ぶ声が響いた。気付けば、中庭に大人が何人か出てきている。
「あ、おとうさま!」
女の子は振り向くと、足元にいたジェフリーを追い越して、ぴょんと地面へ飛び降りた。かなりの高さだったのに、まったくおじけることもなく。
「こら、勝手に外に出たらいけないって言っただろ?」
「ごめんなさーい」
女の子にそっくりな容姿の―――けれど、それよりずっとずっと大きなその人は、小さな金髪頭をぐしゃぐしゃと撫でてから、柱の下で決まり悪そうにする少年を見た。
「お前が見ててくれたのか?」
「……うん」
「そっか、助かったよ。ありがとう」
と、今度はジェフリーの頭をポンポンと軽く叩いた。
「目を離すと何をしでかすかわからないんだ」
「……うん」
ジェフリーはその意見には大いに賛同した。自分も大概悪戯な方だとは思っていたけれど、彼女は輪をかけて悪戯だった。
「サフィー、ひとりでも平気だもん。ひとりで遊べるよ?」
「ん? そうかぁ? この間ドロドロになって帰ってきて、ベアトリクスに叱られるから何とかしてくれって、父さんに泣きついたろう?」
「泣いてないもん」
ジタンおじさんは、ははは、と愉快そうに笑ってから、どうやらもう一人女の子を探している人がいたらしく、「ダガー!」と大声で誰かを呼んだ。
「こっちにいたよ!」
黒髪の女の人が、息せき切って駆け寄ってきた。
「サフィー!」
「ごめーなさい」
ささっと父親の影に隠れる女の子。
「あなたって子はもう!」
「ごめーなさい」
「どうしてお約束を守れないの? お母さまが困るのが楽しいの?」
「……うんん」
「じゃぁ、指切りしたらお約束は守らなきゃダメでしょ?」
「……うん」
女の子はますます父親の足にへばり付いて隠れた。ちょっと滑稽で、ジェフリーはおじさんと目を見合わせて、クスクス笑った。
「ジェフリーが見ててくれたらしい」
ジタンおじさんが説明した。
「まぁ、あなたが?」
ふわりと屈みこむと、女の子のお母さんはジェフリーの顔を覗き込んだ。
「どうもありがとう」
そう言って、柔らかな白い手で両頬を挟まれた。
「大変だったでしょう? どこか怪我はない?」
どこもかしこもふんわりしている女の人だった。自分の母親とあまりに違うので、ジェフリーはぽかんとなってその人を見つめた。
ジェフリーが黙っているので、
「もしかしてどこか痛くした? どうしよう、どこかしら」
と、困ったようにあちこち調べてくれた。
「あ、あの、大丈夫です。どこも痛くないです」
ジェフリーは小さな声で答えた。
「本当?」
すごく心配そうに、そう聞かれる。
「はい」
ジェフリーはもう一度小さな声で答えて、俯いた。何だかそわそわして、落ち着かない。
「大丈夫だよ、ダガー。ブランクがそんな軟には育てちゃいないさ」
ジタンおじさんはおかしそうに笑った。
「でも……本当にどこも痛くない?」
俯いた顔を覗き込まれて、ジェフリーはなぜかものすごく恥ずかしくなってますます俯いた。
俯いたまま、こくこくと頷いた。
やっと信じてくれたらしく、その人は安堵の溜め息を吐いた。
「よかった。怪我させちゃったのかと思ったわ」
ジェフリーはもう一度頭を振って、それを否定した。
「この子のこと、面倒見てくれてありがとう。大変だったでしょうに、優しいのね」
そう言って、今度はふわふわと頭を撫でてくれた。
それで、ジェフリーはそれからしばらく顔を上げられなくなった。
***
「……ェフリー、ジェフリーってば!」
ハッとして、ジェフリーは我に返った。
「ちょっと、どうしたのよボーっとして」
「え?」
サファイアが青い目で怪訝そうに見ていた。
「えーっと……なんだったっけ?」
「だから、初恋が何歳だったのかって話よ。もー、ニヤニヤしながら何思い出してたの? スケベなんだから」
「ス……!!! ち、ちが、だ、大体思い出せって言ったのサフィーだろ!?」
「別に、そんな細かいところまで思い出せなんて言ってないもん。それで?」
「え?」
「え、じゃなくて。何歳だったか思い出せたの?」
「え? えーっと」
目の前でちょっと唇を尖らせているその子を見つめる。成長してはいるけれど、あの頃とあまり変わっていないとも言えた。
それがちょっとおかしかった。
「なによー、またニヤニヤして」
「言ったらサフィーはきっと驚くぜ?」
「何が?」
「俺の初恋の相手」
「え、誰? 知ってる人? まさかリアナじゃないでしょうね!」
「は? 誰があんなガサツ女―――」
「へー、誰がガサツですって?」
ピキ、と空気が裂けたのが、ジェフリーにははっきり見えた。
ぐぎぎぎ、といいそうな首を回して見ると、背後に彼の双子の姉が仁王立ちで睨みつけていた。
-Fin-
伝家の宝刀、バッタの話でした。何だそれ(笑)※緋焔と会った時に仕入れたリアルネタ。
実際の出来事はこんなんじゃなかったはずです。はずというか絶対違う。
しかもバッタがほとんど出てこないという(笑)
緋焔の誕生日も近いので、一応捧げておきます。おめでとう(あんまし嬉しくないと思うけど:笑)
緋焔と話してて思い出したのですが、2世は結構リアルのネタが各所に使われているのです。
別にモデルがいるというわけではないですけどね。ただのインスピレーションとして。
子供時代に色んな思い出を作っておくと、こんな時にも役立ちます(笑)
大人になると見えないものが見えるからなぁ…トトロとか(笑)
この話、ホントはクリスマスの時期なのですが、さすがに背景がありませんでした。
でもバッタが可愛いv 虫嫌いの方はすみませんでした(^^;)
2008.11.9
 Novels Novels  TOP TOP
|  Novels
Novels  TOP
TOP