<3>

「あ、目が覚めた?」
ジタンは数度目を瞬かせたが、ぼんやりと霞んだ視界はなかなか戻らなかった。
たぶん、目の前にいるのはガーネットなのだろう。とりあえず、乾いた喉で、掠れた呻き声のような返事をした。
「大丈夫? どこか痛むところはない?」
不安そうな鈍色の瞳が霞みの中から現れ、ジタンはようやく事態を飲み込んできた。
そうだ、ヤーン―――!
がばっと起き上がったジタンは、しかし体のあちこちから上がった悲鳴に耐え切れずに屈み込んだ。
「ダメよ、まだ完全に回復してないんだから!」
ガーネットが宥めるように言い、再び寝袋の上に横たえてくれた。
「どう……したんだっけ?」
「召喚獣を呼んで、倒してもらったの」
ガーネットは小さく呟いた。
それでジタンは全員助かったらしいことを悟った。安心と共に、情けなさが込み上げてくる。
「ごめん、オレ……」
「うんん。ジタンは、わたしのことを庇ってくれたんだもの。感謝してるの」
ガーネットは変わらず、小声で囁いた。
はっきりしてきた目で辺りを見回す。どうやらテントの中らしい。エーコとビビは眠っているようだった。
「今、真夜中くらいだと思うわ」
それに気付いたガーネットがそう教えてくれた。
「二人ともさっきまで起きてたんだけど、もう遅いから寝てもらったの」
そっか、とジタンは呟くと、布張りの天井を見上げて黙った。
ガーネットもまた、何も言わずに黙っていた。
ジタンは今、何を考えているんだろうか。ガーネットは微かな月明かりに光る青い目をじっと見ていた。
あまりに静かで、遠くでゼムゼレットが「ほう、ほう」と鳴いているのが聞こえた。
やがて、ジタンは緩慢な動きで寝返りを打った。
「ダガーも、もう寝た方がいいよ」
極密やかな声でそう言った。
「うん」
明日、ジタンがまだ回復していなかったらどうしよう。ガーネットは横になりながら考えた。
コンデヤ・パタまで戻って、サラマンダーを呼んで来るとしたら、わたしとビビの二人で行った方がいいだろうか。それともエーコ? でも、ジタンはきっと、わたしたちだけで行かせるのを承知しないだろう。
ガーネットはジタンの背中を見た。
ジタンは道中ずっと、あの背中でいつも庇ってくれていた。お城にいた時は守られるのが当たり前だったから、ありがたいと思いつつも、ガーネットはそのことについて今まであまり深く考えなかったのだ。
―――でも、ジタンが傷つくのを見るのはイヤだと思った。
「ジタン……?」
その背中が微かに震えた気がして、ガーネットは起き上がった。
「寒い?」
返事はない。寒いわけはなかった、この地方は霧の大陸に比べたら暖かいくらいだ。
ガーネットは手をつき、ジタンの顔を覗き込んだ。ジタンはさっきと同じように目を開いて、じっと暗闇を見つめていた。
その目を見て、ガーネットは小さく息を呑んだ。もう少しで叫びそうになるのを押し留める。彼女はその目を知っていた。彼女の母も、同じ目をしていたから―――!
ジタン、と、ガーネットは小さく呼びかけた。
「ジタン……!」
最後は涙声になった。ガーネットはそっと金色の頭に、震える腕を伸ばした。
ジタンが何を考えていたのか、ガーネットにははっきりと判った。ジタンは自分を責めている。自分の存在を疎んでしまったのだ。
悲しくてたまらなかった。母が変わってしまった理由はわかったが、その代償はあまりに大き過ぎた。
ジタンは、知らなくてもよかったことを知ってしまったのだ。
それもやはり運命だと言うなら。神様はあまりにも惨いことをしている。何人たりとも、誰かをこんなに苦しめていいはずはないのに―――!
「……ごめんなさい」
唇から漏れた言葉は、赦罪を求める単語だった。
剥き出しの肩へ温い水滴が落ちる感触に、ジタンは少し身じろいだ。
「ごめんなさい、ジタン」
ガーネットは何度もその言葉を口にした。
その度に涙の滴が落ち、その度にジタンは我を取り戻していった。
どうして、お前が謝ってる?
「ダガー……?」
掠れた声に名を呼ばれ、ガーネットは泣き濡れた顔を上げた。
「泣いてるのか?」
ガーネットは頭を振った。泣いているのではない。ただ、悲しくてたまらないだけで。
ただ、彼を傷つけた運命が恨めしいだけで。
「わたしが、傍にいるわ」
ガーネットは囁いた。
「ずっと傍にいるわ。あなたを一人にしたりしない」
ジタンの唇が「え?」と問いかけの形になり、しかし声は発せられなかった。
「だから、お願い」
―――ナカナイデ。
「お願い……!」
運命になんて、負けてはダメ。
嘗ておじいさまがそうだったように。おばあさまがそうだったように。
わたしたちは、わたしたちの運命になんて、負けてはいけない。
だから、お願い、ジタン。
立ち上がって。負けてしまわないで。
そんなもの蹴散らしてやるって、いつものように笑って見せて―――!
頭に回された細い腕に力がこもり、ジタンは目を閉じた。
そうだ。自分はこの場所を知っている。
いつか帰ってみせると、魂に誓ったあの場所だ。
「ダガー」
ジタンはそっと白い腕に手を触れた。ゆるりと解かれた腕を外し、起き上がる。額と額がくっつきそうなほど近くから、彼女の顔を見据えた。
青い瞳に宿った力の強さに、ガーネットは息を呑んだ。
「オレは、負けない」
そう。
負けるのは簡単だ。
自分が死んで、それで終わり。
でも、それは逃げること。それでは何の解決にもならない。
魂の奥底で、誰かがそう叫んだのを彼は聞いた。
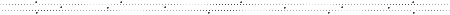
――― あなたを 守りたいの
そっと呟かれたその言葉を、その温もりを、オレは絶対に忘れない。
例え、この身に何が起きても。
-第五章終わり-
 BACK BACK  NEXT NEXT  Novels Novels  TOP TOP
|