|
<2>
翌日。
ガーネットは商業区へ買い物に出かけた。その日は市場が空いていて、いつもより早く用事が済んだ。好都合と、ついでに教会まで足を伸ばしてみた。
ガーネットが女王の位を廃することは、ジタンにも直前まで知らせなかった。ジタンが誰かに洩らすはずがないとガーネットは言い張ったが、ベアトリクスが首を縦に振らなかった。
「例外を許してはいけません、ガーネット様」
そのせいで、ガーネットがリンドブルムへ来た時には、まだ二人で住む家さえも用意できていないほどだった。その上このご時勢で、教会では来る日も来る日も結婚式が立て続けに行われており、数ヶ月先まで予約の取れない状況だったのだ。
式なんてどんなものでもいいとガーネットは言ったが、ジタンは「一生に一度のことだから」と、教会での式にこだわった。ガーネットとて普通の女の子と同じように、好きな人と素敵な教会で、純白のドレスを身に纏い――というオーソドックスな結婚式には一種の憧れを抱いてはいた。しかし、ジタンがまさかそんな風にこだわるなどと思ってもいなかった。
「バカね、ダガーのために決まってるじゃない」
エーコにそう言われて、初めてガーネットはそのことに気付いた。
「ダガーのことを喜ばせたいのよ。ホントは教会で結婚式を挙げるなんて、ジタンには全然興味もないことだと思うわ」
教会の扉を開き、中へ入ってみる。ちょうど式が終わったばかりらしく、まばらに片付けの人が見えた。
ガーネットは思い描いてみた。みんなに祝福されながら、そこで結婚の誓いを立てる彼と自分の姿。白いドレスを纏った自分。隣を歩くジタン。
ジタンに感謝したいと思った。どうでもいいと思っていたはずなのに、そんな風に想像しただけで心が浮き立つのを感じた。
うきうきしながら教会を出て、通りを歩いた。夕暮れの空は赤く染まり、明日の晴天を約束していた。子供たちが歓声を上げながら通り過ぎ、彼らと同じ方向へ家路に着く人々。ガーネットもまた、小さくても幸福なあの家へ帰るのだ。
しかし、ガーネットはエアキャブには乗らなかった。その手前で、知り合いの親子に出会ったのだ。ジタンの職場の上司の妻と、小さな娘だった。
「だから、また明日買ってあげるから」
「イヤ!」
「仕方ないでしょう、また戻ったら時間がかかるんだから」
「イヤ!」
「あの、どうかされましたか?」
ガーネットが声を掛けると、彼女は「まあ」と声を上げて、会釈した。
「こんにちは。今帰り?」
と、買い物袋を見遣る。
「ええ」
ガーネットは微笑んで答えた。
「何かお困りですか?」
そう尋ねると、彼女は眉根を寄せた。
「そうなのよ、ちょっと買い忘れたものがあって」
「今日買ってくれるって約束したもん!」
小さな娘は頬を膨らませて母に抗議した。
確かに、その子を連れて今から混み合う市場に戻るのは難儀そうだった。
「もしよろしかったら、一緒に待ってましょうか」
ガーネットは女の子の頭に手を乗せた。小さな少女は不思議そうに彼女を見上げた。
「でも、ご迷惑でしょう?」
「いいえ、大丈夫です。少しくらい帰りが遅くなったって問題ないですから」
そう言うと、「じゃぁ、お言葉に甘えようかしら」と、彼女は頬に手を当てて考えた。
「どうぞ行ってらしてください」
ガーネットはにっこりと微笑んだ。
しかし、帰りは「少しくらい」でなく遅れることとなる。
ジタンが仕事を終えて帰っても、家には明かりさえ点いていなかった。
ガーネットと小さな少女は、エアキャブ駅の前から忽然と姿を消してしまった。その行方は、ようとして知れなかった。
***
知らせを受けたジタンが詰め所へ駆けつけると、彼の所属する傭兵隊の班長とその妻がいて、彼女はこの世の末のように泣いていた。
「どういうことですか?」
「班長の奥さんが買い忘れたものを買いに市場に戻った隙に、娘さんとあんたの奥さんが行方知れずになったらしい」
近くにいた班員の一人がそう説明した。
「娘を預かって、うちのが市場で用を足すのを待ってくれていたそうだ」
班長が後を継いだ。
「なのに、駅前で二人を見かけたって人間が誰もいなくて」
「変なんですよ。あちこち探したんですけどね、ちっとも見つからないんです」
何人かが口を開く度に、班長の妻はますます泣いた。
「とにかく、今わかっているのは、エアキャブの駅前にいたはずのお前の女房とうちの娘が行方不明になったということ、それだけだ」
班長はすすり泣く妻を宥めながら、そう話をまとめた。ジタンも肯いた。
とにかく、それだけは確かなことらしかった。
ジタンはぎゅっと唇を噛み締めた。一体何が起こったというのだろう? 冷静になろうとするのに、ダガーは無事でいるのだろうかと、そればかりがぐるぐる頭を回った。
「班長!」
班員が一人駆け込んできて、慌てて班長の元に駆けつけた。
「どうした」
「は、犯行声明です!」
「何?!」
紙切れを一枚、机の上に叩き付けるように置いた。
お前の妻と子を預かった。
二人を返して欲しければ、盗人の汚名を着せられた男を解放せよ。
「なんてことだ――!」
班長が唸り声を上げた。
「それじゃぁ、ジタンの奥さんは班長の奥さんと間違えられて……?」
「警備隊に連絡しろ! 早く!」
ジタンは蒼褪めた顔で、その紙切れを見つめていた。
間違いない。
間違いない。
あの、取り留めもない怪文書。
同じ人間に間違いない。
それはあくまで勘に過ぎなかったが、彼にははっきりと確信できた。彼の心に与える印象が全く同じだった。
班員たちが忙しく走り回り始めたが、ジタンはまだ呆然としたように突っ立っていた。ただし、そう見えるだけで、頭の中は目まぐるしく動いていた。
と、すると、あの物盗りと怪文書は関係があるということか?
盗まれた物は何だったか……ポーション、テント、あとは?
「そんなに気落ちするんじゃない」
班長がジタンの肩に手を置いた。
「きっと二人とも無事で帰ってくる」
ジタンは顔を上げた。
「あの……あいつは、ダガーは魔法が使えるんです」
「魔法?」
「それに、ある程度は戦い方も身に付いてます。普通の女の子とは違うんです」
「本当か」
もし相手が何か意図を持って誘拐事件を引き起こしたのだとしたら、きっと二人はまだ無事に違いない。今は一般人だったとしても、元はアレクサンドリア一国を治めた女王、簡単には引かないだろうとジタンは思った。駆け引きは得意分野のはずだ。
「多少の時間稼ぎならできるはずです」
「……わかった」
班員の一人が、申し訳なさそうに会話に割り込み、
「あの、警備隊に引き渡した物盗りは釈放してもらった方がいいですか?」
と、おずおず尋ねた。
班長はしばらくの間考えあぐねていたが、やがて大きく肯いた。
「泳がせて尻尾を掴め」
しかし、それは上手くいかなかった。釈放された男は尾行をまいて行方を眩ました。
相手の言う通りにしたものの、未だ人質は解放される様子がなかった。
手がかりはゼロになった。
行方を追えという班長の怒号が響き渡る中、ジタンは何か妙だと思った。
それなりの訓練を受けた傭兵の尾行を、そんなに簡単に振り切れるものではない。誰か手を貸したに違いない。しかし、外から誰かが手を貸したとしても、とにかくそう簡単に振り切れるものではないはずだ。と、すれば。
「班長」
ジタンは立ち上がった。
「休暇を貰っていいですか」
「何だと」
ぐるりと班員の顔を見回す。全員揃っている。
「今回のことは、オレが参加すべきじゃないと思うんです」
「ジタンさん! それでいいんですか?」
「もし何かあったら、冷静に判断できる自信がない」
ジタンは真剣な目でそう告げた。
班員たちは顔を見合わせた。そんな弱気なことを言うのは、ジタンらしくなかった。しかし、確かに新妻を人質に取られている以上、それは無理もないことだった。
班長は小さく溜め息を吐いた。目に僅かな失望の色を乗せる。
彼はジタンを買っていたのだから、こんな風に隊を離れるのを良しとはしなかった。それでも、自分でそう判断しているのだから致し方ない。
「……わかった。自宅待機に切り替える。何かあったら連絡する」
「お願いします」
難しい顔をしたまま軽く頭を下げると、ジタンは詰め所を出た。
微かに、口元を緩ませる。
こんなことは朝飯前。これでも、役者の端くれなのだ。
とにかく一刻を争う。ジタンは、彼が最も信頼する仲間のいる場所へ走った。
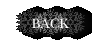 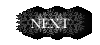  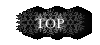
|