|
<4>
「リンドブルムではないかもしれぬな」
フライヤが、ふとそう呟いた。
それに合わせて何人かが頷き、ジタンも「なるほど」と呟いた。
「確かに、この街のことは隅から隅までよく知ってる奴が多いしな」
「うむ。警備隊も傭兵も、人質を隠せそうな場所に心当たりを付けやすい」
「――としたら」
ジタンは顎に手を当てた。
「交通手段から考えたら、アレクサンドリアか、ダリか……」
「田舎は難しいだろう」
サラマンダーが釘を刺した。
「それなりに身を隠せて、ヨソモノが団体で出入りしていても怪しまれないとしたら、エーコはアレクサンドリアって気がするわ」
エーコが手を挙げて意見した。
「私もそう思うのじゃ」
「でも、リンドブルムかもしれない」
ブランクが話に割って入った。
「可能性がある以上、抜かすわけにはいかないだろ」
「そうなんだよな」
ジタンは顎に指を当てて考えた。
「タンタラスでリンドブルムを当たればいい。お前さんたちはアレクサンドリアへ向かえ」
バクーが言うと、「そうっスよ! この街のことなら任せるっス」「おいらたちが適任ずら」と仲間たちが賛同した。
結局、アレクサンドリアへはジタン、サラマンダー、エーコが向かうことになった。あちらにはスタイナーたちもいるからと、フライヤは何かの時のために残ることになった。
エーコはリンドブルムに詳しかったが、公女という身分から、リンドブルムでの単独行動は危険と判断された。
「それに……こういうことはあんまり言いたくないんだけど」
エーコは小さく呟いた。
「何となく、エーコが必要になることがあるかもしれないって思うの」
赤い煉瓦の街並が近づいた時、ジタンは劇場艇の甲板でぎゅっと拳を握り締めた。
この街は、なぜかいつもそうやってジタンを決意に導いた。
ガーネットの故郷であるこの街のどこかに、彼女は捕らえられ、彼の助けを待っているのだろうか。どうにも、そんな気がしてならなかった。
「おっさん!」
「ぬ? ジタンではないか!」
スタイナーは相変わらずガシャガシャとうるさい鎧を鳴らしながら、走り寄ってきた。
ガーネットが王位を廃した後、アレクサンドリアは民主化して議会政治をひいていた。しかし軍部は残ったままだったので、スタイナーもベアトリクスも前の職に留任していた。
「皆揃ってどうしたというのだ?」
「ダガーが誘拐された」
ジタンは声を潜めてそう告げた。
「……な、何だと! 姫さまが!」
「アレクサンドリアへ連れ去られた可能性があるんだ」
「あくまでも『可能性』なんだけどね」
エーコが釘を刺したが、女王の位を降りたガーネットを未だに主人と思っているスタイナーには効果がなかった。
「ご安心ください姫さま! このスタイナーめが必ずお救いするのであります!!」
「……とにかく、プルート隊の奴らに頼んで、怪しいグループを見かけた人がいないか調べてくれよ」
ジタンが呆れた顔でそう言うと、「おお! 早速集合させるのである」とスタイナーは走って行ってしまった。
「相変わらず忙しない奴だなぁ、おっさん……」
「クイナを探しましょ」
エーコはジタンを引っ張った。
クイナはすぐに見つかった。ルビィのコネで「明けの明星亭」に再就職していた。しかも、運良くベアトリクスと部下の数人が遅めの昼食を食べに訪れていた。
突然現れたジタンたちにみんな驚いていたが、訳を聞くとベアトリクスたちは昼食を中断して店を飛び出していった。
「そういえば、変な噂を聞いたアル」
クイナは思い出したように言った。
「下町の方に空き倉庫がアルね、あの辺りでよく人が出入りしているって話アル」
「なんかそれ怪しいな」
ジタンが呟いた。
「怪しいも怪しいアル」
クイナも頷いた。
***
ガーネットは目を開けた。
正確な時刻はわからない。あれから一度日が暮れ、再び昇って随分と時間がたっていた。
「お姉ちゃん」
ぴったりと身を寄せたまま、ケイトが呼んだ。
「どうしたの? 手が痛い?」
ロープが食い込んだ手首が傷むのは、ガーネットも同じだった。
「ちょっと……頼んでみようか」
今日も見張りはキーとニーが二人でしていて、時折どちらかが休憩で外へ出て行った。今はちょうどお喋りなキーが休憩中で、無口なニーが梯子の二段目に腰掛けて剣を磨いていた。
「あの」
ガーネットは意を決して声を掛けた。
「腕が痛むんです。ロープを少し緩めていただけませんか?」
ニーが顔を上げた。鋭い目つきに、ガーネットは一瞬怯む。やっぱり、陽気なキーに頼めばよかった。
「せめてこの子の方だけでも」
言い募ると、やがて彼は腰を上げて、近寄ってきた。
無言のまま背後へ周り、ケイトのロープを大幅に緩め、続いてガーネットのも緩めてくれる。
「あの……ありがとう。楽になりました」
何も言わずに元の位置へ戻ろうとするニーに、ガーネットはにっこり笑いかけた。
行きかけた彼が、ふと振り向いた。ガーネットが見上げると、何か言いたげな目をした。
「外はどうなってるんでしょうか」
ガーネットは話を続けてみた。じっと、鋭い目でニーが見つめる。
「私たち、何もわからなくて不安なんです。何が起きてるんですか? 一体、あなた方は……」
彼が再び足元へ寄ってきたので、ガーネットは口を閉じた。怒らせたか? しかし彼の表情はそうは言っていない。
ニーはガーネットの側に屈みこむと、指で地面に字を書き始めた。
『俺は』
そう書いて、一度指が止まる。
ガーネットが黙ったまま見ていると、再び指が動いて
『こんなやり方は気に食わない』
そう書いた。
「こんな?」
『多くの人間に罪はない。それなのに、被害を被るのはいつも弱者だ』
「被害……」
自分たちのことを言っているのだろうか?
ニーは一度地面を擦って字を消し、また書き始めた。
『あいつらは、リンドブルムの城に爆弾を仕掛ける計画をしている』
「……えっ?」
『シド大公を暗殺するつもりだ』
ガーネットが蒼白になると、ニーは彼女の顔を見て、小さく頷いた。
『頼む、計画を止めてくれ』
どうして、と小さく呟きかけて、ガーネットも右手の人差し指を地面へ這わせた。さっきロープを緩めてもらった時から、両手とも自由になっていたのだ。
『どうしてあなたはそれを私に?』
『あんたは只者じゃない。そう思うからだ』
『でも、こんなことを教えたと知られれば、あなたに危険が及ぶわ』
『俺はどうなっても構わない。俺に何かあるとすれば、それは俺の落ち度だ』
落ち度、とガーネットが呟いた。
「どうすれば?」
『止めて欲しい。爆弾がどこに仕掛けられたか、俺は知らない。俺たちは計画の詳細を知らされていないんだ。でも、あんたならきっと突き止める』
頼む、と唇が動いたけれど、声は出なかった。
***
ガーネットはケイトの手を握って立ち上がった。ニーが用心深い顔で辺りを窺う。食事に行ったキーはまだ戻らなかった。
ガーネットが見ると、ニーが頷いた。
「ケイト」
少女が見上げる。
「わたしたち、ここから脱出しなければならないの」
「うん」
「あの、天井の側の窓がわかる?」
指差した先を見上げ、こくりと頷く。
「うん、わかる」
「あそこから、外へ出るのよ」
ケイトは眩しそうに目を細めた。
「でも、高いよ」
「大丈夫。私も一緒に登るからね」
うん、と少女は頷いた。
三階か四階くらいの高さがあった。細い梯子が途中まで伸びていたが、窓の側までは梁を伝わねばならない。
ケイトは存外に器用で、体が軽いこともあってするすると登った。
ニーが心配そうに見上げているのが殊更小さく見えた。ガーネットは子供の頃からお転婆な方だったが――そのせいで、出会ったばかりの夫を驚かせた――、それでも足が竦んだ。
「窓が開くか試してみるわ」
光採りのための窓で、普通には開かなかった。しばらく試してみると、どこかの金具が外れて、建付けの悪い窓のようにカタリと開いた。
しかし、窓枠は思ったよりもずっと小さい。
ガーネットは顔を出してみた。辺りを見渡して、思わず小さく声を漏らす。
見紛うはずがなかった。毎日城の窓から眺めた赤レンガの街並み。
「アレクサンドリア……!」
そこは、彼女の故郷の街だった。
「お姉ちゃん」
少女が心配そうに見つめる。
ガーネットも振り向いた。そうだ、彼女一人ならこの小さな窓も抜けられる。
――しかし、この子一人で果たして助けを呼びに行けるか?
もし奴らに見つかったら?
その時だった。
真下の通りを、誰かが歩いているのが見えた。小さな点のようだったが、金色の頭がゆらゆらと揺れているのだと判別できた。
そう、ガーネットには目を凝らさなくてもわかった。
「ジタン――!」
大声で呼ぶわけにはいかなかった。誰かに気付かれるかもしれない。
ガーネットはとっさに、左手の薬指から指輪を抜き、ジタンの目の前を目掛けて投げつけた。
指輪は思ったとおりの場所に落ち、ジタンがはっとして顔を上げた。
「ダ――−!!」
「しっ」
ガーネットが指を口元に当てると、それを見て取ったジタンは自分の口を手で塞いで、辺りを見渡した。
幸い、誰にも見られていないようだ。
「すぐ助ける」
ジタンが小声でそう囁いた。しかし、ガーネットは首を横に振る。
自分がここから出るには、窓枠を大きく壊さねばならない。そうなれば、誰かに気付かれるリスクが高まる。それに、ガーネットもケイトもいないとなれば、すぐに追っ手がかかるに違いない。
ニーは「シド大公が危ない」と言っていた。どこかに爆弾が仕掛けられているのだと。
もし人質が抜け出したと知れれば、事態が更に悪化するかもしれない。それに、奴らの動きも掴めなくなってしまう。
「ケイト、よく聞いて」
ガーネットは自分のブラウスの裾を破りながら、少女に言い聞かせた。
「下にジタンがいるわ……彼を知っているわね? お父さんの部下よ」
「うん、知ってる」
ケイトが頷いたのを確認して、ガーネットは窓の桟に溜まっていた埃を指に取り、破いた布に字を書く。
『おじさまが危な』
そこまで書いて、下でニーが慌てたように柱を叩くのが聞こえた。
誰かが戻ってくる合図だ。
「ケイト、これを持ってジタンのところへ」
「え、でも……」
後ろにいたケイトを窓の側へ行かせる。彼女は怯んだように呟いた。
「怖いよ」
「大丈夫よ、受け止めてくれるわ」
涙目の少女に、ガーネットは微笑みながら頷いた。
「ジタンを信じて。何があっても絶対に受け止めてくれるから」
こちらを見上げていたジタンが、何をする気かを悟ったらしい。とっさに両手を広げて体制を整えた。
「さあ、頑張って」
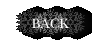 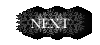  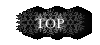
|