|
<5>
「よう、悪いな。遅くなった」
キーが朗らかな声で入ってきたのは、ガーネットが梁から降り、ケイトから脱がせたカーディガンを小麦の袋に被せて、隣に括りつけた直後だった。
「お前もメシ行ってこいよ。ほら、俺はねえちゃんたちの食いもん用意してきたからよ」
ニーが黙ったまま右手を突き出すと、キーは「おりょ?」と声を上げた。
「なんだよ、お前が食わすのか?」
頷きこそしないものの、ニーは否定しなかった。
それもそのはず、今はガーネットの影になって見えにくいが、近づかれるとケイトがいないことが丸わかりだ。
ニーはくいっと顎をしゃくった。
「そうかぁ? じゃぁ、俺っちはもう少し休んでくるわ。悪いな」
キーが行ってしまうと、ニーはほっと息を吐いて、ガーネットに近寄ってきた。
食事の乗ったトレイを足元へ置いてくれる。
「ありがとう」
ガーネットが礼を言うと、ニーは曖昧に首を振った。
『俺は裏切り者だ』
ニーの右手はそう綴った。
『自分の家族のために、他の多くの人間を犠牲にしようとしている』
「家族?」
ガーネットが訊くと、ニーは小さく頷いた。
『あんたたちと同じだ。奴らに取られた』
そう指が綴る途中で、ガーネットが喉の奥で短く悲鳴を漏らした。
『こんなことになるなら、いっそ俺は』
「いいえ」
最後まで見る前に、ガーネットが頭を振った。
『わたしがあなたでも、同じことをした……きっとどんな人でも、あなたと同じようにしたわ』
ニーはじっとガーネットを見つめて、小さく息を吐いた。
「大切な人を守るためなら、何をも犠牲にできる。それが人間だもの」
***
その頃、アレクサンドリアには別の騒ぎが起きていた。その連絡を受けたベアトリクス将軍が、小さく呻き声を漏らしたくらいだった。
「今言ったことをもう一度繰り返して」
将軍に請われ、伝達係はさっきと同じ言葉を繰り返した。
「10分ほど前、ダリ村に爆薬が仕掛けられている、という通告がありました」
「規模は」
「不明ですが、かなりの量だということで、配線等も見受けられたということです」
「……爆弾ということ?」
「そう思われます」
「私たちのところで、処理できる人材は」
別の係が立ち上がり、「難しいかと思われます」と発言した。
「配線の種類によっては、専門家の意見なく手をつけることで、余計に危険を増幅させる可能性があります」
ベアトリクスは小さく息を吐いた。
「とにかく、一刻を争う可能性があります。村民の避難と、リンドブルムへの応援要請を急いでください」
ケイトを保護した後、ジタンはアレクサンドリア城へ戻った。すぐにでもガーネットを救出したかったが、少女を連れたまま、準備もなく一人で乗り込んでも結果は知れている。
それに、ガーネットからの伝言をシドに伝える必要もあった。
「爆弾処理班?」
リンドブルムへ無線を繋ぐと、そんな不穏な単語が飛び込んできた。
『そうじゃ。ダリ村へ爆弾処理班を送り込んで欲しいと。規模もわからぬということじゃから、応援部隊を三隊と、処理班の五名を全員行かせた』
シドはそう答えた。
「……全員行ったのか?」
そんな話は聞いていない。今回のことと何か関係があるのだろうか……?
『そうじゃが、何か問題があるのか?』
「ダガーが」
その名が出た瞬間、シドが「姫は無事なのか」と聞こうとしたが、ジタンはその隙を与えなかった。
「おっさんが危ないって、そういうメッセージを寄越したんだ」
『ワシがか?』
「ああ。直接話せなかったからよくはわかんないんだ。でも、とにかくそうらしい。ダガーの言うことだから間違いはないはずだと思う。くれぐれも注意してくれよ。――それから、班長の娘は無事に保護したから、班の方にはそう伝えてくれないか」
『なぜ娘が助かって、姫とはまだ直接話せないんじゃ』
「あいつは、まだ」
小さく空気を吐く。
「まだ、人質になったままなんだ」
ジタンが無線室から出てくると、待っていたとばかりにスタイナーが駆け寄ってきた。
「現場を特定できたと聞いたのである」
「ああ、クイナが言ってた空き倉庫の一つだ。相手の人数は分からないが……たぶん少ない数ではないと思う」
説明しながら、小窓から顔を出していたガーネットの姿が目にちらついた。ケイトの話では無事らしいが、自分で確かめなければ落ち着かなかった。
「プルート隊は全隊そちらへ向かうのである」
「ああ」
サラマンダーを見遣ると、彼はちらりとジタンを見ただけで、何も言わなかった。
「早く行きましょう!」
エーコが飛び上がった。
***
『ベアトリクス将軍!』
無線室に再び声が届いた時、ジタンたちとプルート隊は既にその場を立ち去った後だった。
『ベアトリクス将軍、ご報告です。ダリ村の爆弾騒ぎは偽情報です』
「偽?」
まだ残っていたベアトリクスが、その無線に首を傾げた。
『明らかな偽物です。一目で分かるような代物です』
「なぜそのような――最初の知らせを受けた者は?」
「それが、ベアトリクス将軍……」
ベアトリクス隊の一人が困ったように進み出た。
「誰も、知らないのです」
「知らない?」
「はい。誰が最初の知らせを受けたのか、まったく分かりません」
「どういうこと?」
その瞬間、ベアトリクスははっとして立ち上がった。
「まさか――罠、か」
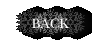 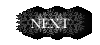  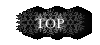
|