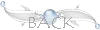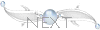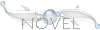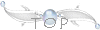|
<3>
「シド様、わたくし、今日はパン屋さんですの。ですから、シド様はお客様をしてくださいませ」
と、ヒルダは頬を薔薇色に染め、菫色の瞳をキランキランに輝かせてそう言った。
「……ヒルダ、そういう遊びは小さな子供がやるのではないのか?」
と、そう言えば、少女はむっとした顔をして、数日口を利いてくれないのはわかっていた。ので、シドはそれを呑み込み、「わかった」と請け負った。
「何にいたしましょうか?」
「フランスパンを一つもらおうか」
「まぁ、メロンパンの方が美味しいですのよ」
……そうだ、今日のおやつにどうしてもと、料理長にメロンパンを用意させたとオルベルタから聞いたばかりだった。
「では、それをもらおう」
ヒルダはニコニコと、お皿に丸いパンを載せた。
「お茶の時間に、一緒に頂きましょうね」
出だしは最悪だったが、夜中にホームシックになったのを慰めてやってから、ヒルダは随分シドに懐いてくれるようになっていた。
ニコニコと子供らしい笑顔も見せるようになったし、ままごとに誘ってくれるようにもなったし、お茶の時間には自分の隣に座っておやつを食べてもくれた。
……何かが間違っているという感は否めなかったが。
夜眠る時には、シドの寝着をぎゅっと握り締め、胸元にうずくまるようにして眠っていた。あれ以来、ホームシックで夜中に目を覚まして泣くこともなかった。
が、それ以上の進展は何もなかった。
とりあえず、「優しいお兄さま」くらいまでには昇格したらしい。一日中べったり張り付いている日もあったくらいだ。
しかし、少しでもヘソを曲げようものなら、一言たりとも口を利いてくれないのだった。
「調子はどうじゃ」
と、父君の大公が笑いを含んだ声で尋ねたのは、その日の夕食時だった。
ここしばらくはヒルダと二人きりで夕食をとっていたが、今日は両親とも揃っての会食の日で、席に着いてからずっとヒルダは緊張しっぱなしだった。シドはそれが忍びなくて、食事中ずっと気になって仕方がなかった。
「仲良うやっておるのか?」
ヒルダがはっとして顔を上げた。どうしてこんな日に限ってこんな食べづらいエビのような料理を出すのかと、シドが溜め息を吐いたのと同時だった。
「はい、仲良くしております」
と、ヒルダは鹿爪らしく答えた。
「シドに意地悪はされておらぬか?」
大公は尚も面白そうにそう訊いた。
「えっと……」
ヒルダは一瞬俯いて、答えに詰まった。どうしてそこで詰まるのかと、シドは背中に冷や汗を掻いた。この父親は、ますます面白がるに決まっている。
「あの」
段々頬が赤く染まっていくのが、遠くに控えていた給仕係にも見えたほどだった。ヒルダはあっという間に真っ赤になってしまった。
それを見たシドまでもが、訳もなく耳を赤くした。
「おほほ、可愛いらしいですこと」
と、大公妃が朗らかに笑った。
「何か意地悪をされたら、すぐこの父に言うのだぞ」
大公がそう念を押すと、ヒルダは吃驚してこくこくと頷いた。
「まぁ、そういうことは母に話す方がずっとやりやすいでしょうのに」
と、大公妃がまた朗らかに笑った。
「シドを叱り付けるなら父が適役であろう」
「あら、ヒルダを優しく慰めるなら母が適役ですわ」
父君と母君は、それからたっぷり十五分は、二人で「どちらが適役か」を議論し続けた。
その隙に、シドはテーブルを立ち上がった。
「父上、母上。ヒルダも疲れたでしょうし、そろそろお暇いたします」
ヒルダ、と呼ばれて、ケーキを食べていた少女は驚いたように彼を見上げた。
「行くぞ」
「でも……」
大好きなチョコレートのケーキなのに……と、呟きかけたヒルダの椅子を引いた。
これ以上、この場にこのいたいけな少女を晒していたくなかった。―――どいつもこいつも、興味津々の目で見やがって。
「酷いですわ」
急いで暇の挨拶をし、食堂を出てすぐに、ヒルダはそう言った。
「せっかくご両親とのお食事でしたのに」
「良いのじゃ」
「でも、こんなに急いで出てきてしまったら、がっかりされますわ」
「せぬから良い」
「でも」
「ケーキなら、今度街へ降りた日に、リンドブルム一美味いというパティシエの店から買って帰ってやるから、今日は諦めよ」
その瞬間、ヒルダはぷぅと頬を膨らませた。
「そんなこと言っておりませんのに」
部屋まで戻ると、召使たちを追い払って、やっとシドはほっとした。
最近、自分はどうもヒルダのことに神経質になっている気がする。
興味本位でジロジロと見られているのが、不憫で仕方ないのだ。それは、両親でも同じことだった。
「お疲れですの?」
長椅子にぐったりと凭れている公子に、彼女は不安そうに寄り添ってきた。椅子の足元に敷かれた敷物の上にペタリと腰を下ろして、その顔を覗き込もうとする。
「もしかして、わたくし何か粗相をいたしまして……?」
悲しそうに訊くので、シドは「そんなことはなかった」と太鼓判を押した。
「もっと楽しそうにお話しをしなければならなかったのは、わかっているのですけれど……」
「気にするな」
「そのことを、怒ってらっしゃいますの?」
そう訊く声は、なんだか泣き出しそうに震えているようだった。
「ヒルダ」
シドは腕を伸ばし、蜂蜜色の頭を撫でた。
「もう休もう。少し眠たいだけじゃ」
確かに公子は眠そうに見えたので、すぐに納得して、ヒルダはその支度を整えるためにパタパタと走り回った。シドは、その様子を長椅子に寝そべったまま見ていた。
まるで可愛らしいメイドのようだったけれど、それと違うのは、恐ろしく手際が悪いことと、どう考えてもこれから寝る人間が使うとは思えない道具を揃えていることだった。
「ヒルダ、そんなものを出してどうするのだ」
「え? 違いますの?」
彼女は驚いたように立ち止まった。
「ばあやは、こうやって世話してくれましたわ」
ヒルダのばあや……実家で世話してくれたその人が一体どんな人間だったのか、少し知りたいとシドは思った。
|