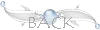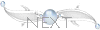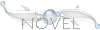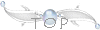|
<5>
カタン、と窓が鳴った。
ヒルダはビクッと震えて、布団の中に潜り込んだ。
大きな城で、夜になればお化けが出そうな古い城で、側には誰もいなくて、ばあやも、お父さまもいなくて。
一人で眠ることなんてなかったから、ヒルダは怖くて悲しくて寂しくて、思い切り泣き出したいくらいだった。
しかし、泣けばきっとシド公子が呼ばれるだろうし、そうなったら彼に縋り付いてしまって、あの、よその女の人と一晩過ごしたらしいことを許してしまうだろうと思った。
それだけは許せなくて、ヒルダは布団の中で必死に頭を振って頑張っていた。
カタカタカタ、と、窓は不気味に鳴った。
恐ろしくて恐ろしくて、まるで頭が氷水に浸かったように冷えた。手足も冷たくなって、心臓だけがドキドキと早鐘のように鳴り続けていた。
ヒルダは、優しく抱き締めてくれる腕が恋しくて、泣き出しそうだった。
最初は、この人は女の人に慣れていて、だからそんな風に抱き締めるのだと思っていた。
でも段々、召使の人たちの話を聞いていると、女の人に慣れている人はそんな風に優しく抱き締めるものではないような気がしてきていた。
ばあやの言っていたことと違う、と、ヒルダは思った。
結婚式の夜は、お淑やかにして、目はずっと下を向いて、返事は「はい」だけと言われていたのに、ヒルダはその言いつけを上手く守れなかった。
そうしていれば、公子様はお優しくしてくださいますからね、と、ばあやは言っていた。だから、言いつけを守らなかったから、優しくしてもらえないのだとヒルダは悲しかった。
でも、夜中に悲しくなって泣いていたら、彼はとても優しくしてくれたのだった。お父さまよりも優しくしてくれて、ヒルダはそれで、この人はとても優しい人なのだと嬉しくなった。
しかし、召使の人たちの言っていることは、そういうことではないような気がした。そんな風に優しいのは、何かとても間違ったことのようだった。本当は、もっと意地悪なことをされるはず、らしかった。
ヒルダは、よくわからなくなって混乱した。
―――だって、シド様は、お休みなさいのキスだってなさらないもの。
綺麗な大人の女の人たちと色んな噂を立てた人だから、こんなおちびちゃんには飽きてしまったのだとヒルダは思った。本当はもっと前から飽きていて、でも、お父さまのお決めになった結婚だからと我慢されていたに違いないのだと。
それで、自分が腹を立てて一緒に休まないと言ったから、清々となさって、今日も女の人と遊びに行ってしまったのかもしれないと思った。
そう思ったら、ますます悲しくなって、遂に小さく啜り泣いた。
「実家へ帰ってよい」と言われるかと思うと、窓がカタカタ鳴るよりも恐ろしかった。
もう優しく抱き締めて一緒に寝てくださらないのかと思うと、悲しくて悲しくて胸が潰れるほどだったのだ。
だから、きっと自分は公子様がとても好きになってしまったのだろうと、ヒルダはそう思ったのだった。
せめて、謝ってくださったら―――わたくし、すぐにお部屋に戻って、また大人しくシド様のお隣で眠れるのに。
その時だった。部屋の扉が大きくカタンと鳴った。
ヒルダは思わず飛び上がるほど驚いて、寝台の上に起き上がった。
誰が来たのだろう。召使の人の誰かだろうか。
でも、彼女が眠っている時に誰かが来るはずはなかった。
心臓が口から飛び出そうなほど鳴っていた。
もしかしたらシド公子が謝りに来てくれたのかもしれないと、彼女は一瞬そう思った。
そう思ったら、体が勝手に動いて、部屋の扉を開けていた。
廊下には、誰もいなかった。
ヒルダは顔だけを出して、キョロキョロと辺りを見回した。遠くで衛兵が勤務の交代をしているのが見えたが、他には何も見えなかった。
ただの空耳かもしれない。
ヒルダは扉を閉めて、またベッドへ戻ろうとした。
しかし、今度は窓がガタンと大きな音を立てた。
思わず悲鳴を上げて、ヒルダは部屋の隅に飛び退いた。
窓はガタガタと激しく鳴り続けた。そしてその窓の向こうで、何か白いものがふわりと揺らめいた。
その瞬間、ヒルダはあらん限りの声で叫んでいた。
***
丁度廊下を曲がった瞬間、その悲鳴が彼の耳に飛び込んできた。
三つ目だ、そう判断して、衛兵たちが駆けつけるより早くその部屋に飛び込んでいた。
「ヒルダ!」
恐慌状態に陥って、部屋の隅で両耳を塞いだまま、彼女は金切り声を上げていた。
「ヒルダ、落ち着きなさい」
激しく震える背中を抱いてやっても、悲鳴は止まなかった。
「目を開けよ、ワシじゃ!」
「どうされましたか!?」
衛兵が駆け込んできて、二人が一緒にいるのを見て吃驚し、慌てて「し、失礼いたしましたー!」と去っていった。
しかし、シドにはそんなものに構っている暇はなかった。
根気強く名前を呼び続けると、やっと叫び声が止まって、次の瞬間にはヒルダは失神してしまった。
今度は、シドが我を忘れる番だった。
|