いつか帰るところ(Garnet ver.)
<1>
ヒルダガルデ3号は、荒れ狂う気流の中、空へと舞い上がった。
地上では暴れ出したイーファの樹の根がのたうち、土煙を上げている。
その中にたった一人、空を仰いで彼は立っていた。
ガーネットの胸に、恐ろしく大きな不安が去来する。
―――どうしよう。
風の中にあっても瞬きもせず、飛空艇から身を乗り出すように、彼女は彼の姿を見つめていた。
……どうしよう。もし、もしも―――。
もしも、二度と再び生きて会うことがなかったら!
次第に小さくなるその姿に、ガーネットは思わず叫び出したいほどだった。
……行かないで! 戻ってきて!!
ガーネットが最後に見たジタンの姿は、金色に光る髪と尻尾を風に揺らし、飛空艇を仰いでふっと笑ったところだった。
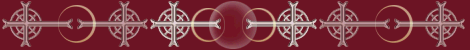
霧が消えた。
これはつまり、再び霧機関が使用できなくなることを意味する。
それでも、イーファの樹の暴走が止まるまで、全ての飛空艇はそこに留まっていた。
彼は戻ってくる。
それだけを信じて……。
―――しかし。
その後、一週間待っても、彼は姿を現さなかった。
イーファの樹の様子を見ていた人々は、誰もが誰も、思っていた。
……あれでは、助かるまい。
霧は完全に消えかかっており、もはや一刻の猶予もなかった。
ヒルダガルデ3号は蒸気機関で飛べたが、ベアトリクスはとにかくガーネットを連れ帰ると言って聞かなかった。
無理もないことだ。
いつまたイーファが暴走してもおかしくない。その上、このままここに留まれば、ガーネットが次に何をしようとするか、明白な事実だったからだ。
それでなくとも彼女は、何度もかの木の根元へ行こうとしたのだから。
「ガーネット様、とにかくアレクサンドリアへお戻りください。お気持ちはお察ししますが、しかし……」
ベアトリクスは跪き、注意深く訴えた。
「霧が消え、国も混乱しておりましょう。女王陛下不在では、何が起こるとも……」
ガーネットは目を閉じた。
泣かなかった。
彼女はあれ以来、一度も泣かなかった。
少なくとも、人の目のあるところでは泣かなかったのだ。
「……わかりました」
ガーネットは苦しげに言った。
帰りたくはなかった。
出来ることなら、永遠に、彼が帰るまでこの地に留まりたかった。
でも、彼は言ったのだ。
「あなた様を誘拐するお約束は、残念ながらここまでです」
と。
それは明らかに、ガーネットに「帰れ」と言っているに等しかった。
帰らなければ。
私の帰るべき場所に帰らなければ……。
ガーネットは、死ぬより辛いと思った。
身を引き裂かれ、胸をえぐられるより辛かった。
***
随分久しぶりなように思う。
アレクサンドリアの町。
町並みは破壊の限りにあい、今は見る影もなかったが、それでもここはガーネットの故郷だった。
レッドーローズに乗り換え、スタイナー、ベアトリクスと共に戻ったガーネット。
町中の人々は静かに、女王の帰りを喜んだ。
「お帰りなさいませ」
「よくぞご無事で……」
しかし、人々の言葉はむなしく心を過ぎ去るばかりだ。
城へ戻っても、ガーネットの心は何も捕らえなかった。
「三日後に、戴冠即位の儀を執り行いまして、その後、リンドブルム、ブルメシア両国との和議話し合い、城の修理修復と順を追いまして……」
「ガーネット様、町の被害はこのようになっております。お留守の間に多少の改善は見られますが、今だ治安も戻らず……」
「霧機関が全面的に使用不可能となりましたので、急ぎ蒸気機関の飛空艇を建造していただくよう、リンドブルムに書状を……」
ガーネットの心は留守だったにせよ、女王としての仕事にはある種の責任感を感じずにはいられなかった。
第一、町を壊したのは自分の責任だ。
いや、何もかも、全て自分のせいのような気さえした。
「ガーネット様は長旅のお疲れがあります。そういったことはまた明日以降に」
ベアトリクスが横から大臣たちに釘を刺し、ガーネットを部屋へ連れ戻した。
「ガーネット様、どうぞ今宵はゆっくりお休みになられてください。すぐに支度の者が参りますので」
ベアトリクスは敬礼すると、部屋を去っていった。
見慣れた部屋。
大きなベッド、窓からは西日が射し込んでいる。
あの日、あの窓から、空を飛ぶ鳥に願いを託した。
どうか、私を空へ連れていって、と。
望み通り、一人の男が彼女をさらってくれた。
どんな時も、隣にいて、支えてくれた人。
でも。
こんなにもその存在が自分にとって大切だったなんて。
見えなくなった影を求めて、その時初めて悟るだなんて。
ガーネットは窓を押し開けた。
お願い、帰ってきて。ジタン……!
| 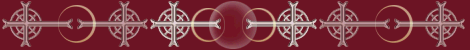
 NEXT
NEXT  Novels
Novels  TOP
TOP
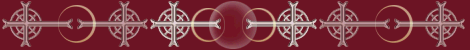
 NEXT
NEXT  Novels
Novels  TOP
TOP