|
<2> 母ブラネ女王はすっかり変わってしまった。 見も知らぬ人間が始終城を出入りし、ガーネットには昼夜を問わず見張りがついていた。 悲しかった。 あんなに優しい母だったのに、今では何かに取り憑かれたように戦いを求め、ひどく荒々しげだった。 そんな日々の中で、ガーネットは夜毎同じ夢を見てるようになっていた。 始めは、濃い霧の中のように、くすんでぼやけた情景でしかなかった。 大きな暗い海が広がり、恐ろしいほど高い波が立っていた。 恐怖に駆られ、彼女は真夜中に何度も目を覚ました。 やがて日が経つにつれ、夢は次第に詳細な情景となった。 ボロボロの小さな小舟。真黒な空。灰色の雲。 強く打ち付ける雨。 耳元で響く風の音。小さな悲鳴。 自分の体を抱き締める、暖かい腕。 ―――自分? 目に浮かぶのは、黒い髪に黒い瞳の、優しい顔立ちをした女の人。 そして、小さな小さな女の子。 母親と、娘。 娘は、自分だ。 ガーネットは強く感じだ。 あれは自分だと。 でも……アレクサンドリアで生まれ育った自分がなぜ小さな小舟で嵐の海を? 一緒にいる女の人も、母とは似ても似つかない。 ―――なぜ? 不安な気持ちは、母ブラネの奇行を危惧する心とともに、どんどんと膨らんでいった。 思えば、母はあの日からずっと暗闇を歩き続けてきたのだ。 あの、父が死んだ日から。 やっと見つけた光明が尋常ならざる危険な光だと、母に気付かせる方法はないのだろうか? ガーネットは悩んでいた。 ずっとずっと、毎日そのことばかり考えていた。 なぜ? なぜ、自分が嵐の海を? なぜ、母はおかしくなってしまったのか? 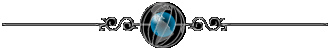 「……劇場艇?」 「そう、お前の十六歳の誕生日にね。お前の好きな『君の小鳥になりたい』を演じさせることになっているのだよ」 母は穏やかに微笑んだ。 「お母さま……ありがとうございます」 ガーネットは深々と頭を下げて礼を言った。 「お前が喜ぶことならどんなことだってしてあげるとも。シド大公に頼んで、わざわざリンドブルム一の人気劇団を呼んだのだからね」 「リンドブルム……シドおじさまが」 ガーネットの小さな呟きは、幸いにも聞き咎められなかった。 1799年暮れ。ガーネットは、不意に母から芝居興行の話を聞かされた。 ガーネットは芝居が好きだった。 芝居好きの両親の影響も然り、トットから教わったエイヴォン卿の戯曲集も好きだった。 母は変わってしまったが、今でも芝居好きだけは変わっていなかったのだ。 ガーネットは嬉しかった。 ひと時、昔の母に戻ったかもしれないとさえ思ったほどだった。 ―――しかし、そんなはずはなかった。 母は傍目にも快方へ向かっているとは言えなかった。 時には、自分への愛情さえ歪んだものに見えた。 恐怖感が募る。 このままにしておいてはいけない。 *** 1800年1月1日。新年が明けたその日、ガーネットは二週間後にアレクサンドリアを訪れる劇場艇へ上手く忍び込み、リンドブルムのシド大公に謁見することを決意した。 計画は念入りに組んだ。 危険な賭けだったが、母を元の母に戻すためにはシド大公の力が必要だと彼女は考えた。 自分が行くしかないのだ―――と。 |
 BACK
BACK