|
<3>
人混みを逆流して、ブランクもまたアジトに舞い戻っていた。
アジトの辺りからでは家の屋根が邪魔して花火がよく見えないという理由から、狩猟祭の夜に人がいることは珍しい。
誰もいない通りを走り抜け、明かりの落ちた居間から階段へ。
ルビィの部屋の扉は、ほんの少しだけ開いていた。
中は真っ暗だ。
「……ルビィ?」
そっと部屋へ滑り込む。
窓のそばの椅子に座ったまま壁に寄り掛かり、ルビィはぼんやりと外を眺めていた。
何も言わなかった。
いつもなら爆発したり猛烈に噛みついたりしてくるルビィだから、こう黙り込まれると、どうしたらいいかブランクにもわからない。
「―――花火、見ないのか?」
ようやく言った言葉は、一言それだけだった。
ルビィはちらりとブランクを見、また窓の外へ目線を移した。
「さっきの人と、見たったらええやん」
「誰のこと言ってんだよ」
「優しそうな人やったね」
やっぱり、と、ブランクは溜め息をついた。
「お前さ、誤解してるだろ」
ギッと、ルビィはブランクを睨んだ。
「誤解やて?」
「そうだよ。さっき話してたのはただの知り合い。この間、商業区の駅で迷子になってた男の子を家まで送ったって話、しただろ? その母親」
「え……?」
「側に旦那と子供、いたじゃないか。よく見ろよな」
ルビーはブランクを見つめたまましばらく瞬きを繰り返していたが、やがてクスクスと小さな笑いを漏らした。
「なんや、そうやったんや」
「当たり前だろ」
「そやね、あんたがそんなに器用なわけないんやった」
何だよそれ、と、ブランクは不機嫌そうに顔を背けた。
「アホやなぁ」
そんなブランクを尻目に、ルビィはしばらく笑い続けていた。
―――幾分、乾いた笑い声だった。
微かな月明かりの中、それでも表情まで見えてしまう自分が恨めしいとブランクは思う。
いつもそんな顔をするから……踏み込めないでいる自分。
心の奥底に、悲しい笑顔で語った彼女の父親の話がいつまでも引っかかっている。
|
『うちな、父親にひどい目に合わされてたん。実の娘にするようなことやない……ことをな』
|
けど、平気だから。
と。
彼女は精一杯笑って見せた。
―――嘘だ。
自分にわからないわけがない。あいつは傷ついてる。
それは、決して触れてはならない深い傷で。
今でも、彼女を苦しめ続ける傷で。
自分ではどうしようもできない傷で……
「あ」
と、ルビィが声を上げたのと同時に、どん、と花火の音が一つ、耳へと入ってきた。
「始まってもうたわ」
ルビィは苦笑いしながら窓辺に立ち上がった。
「今からでも遅くないだろ。行こうぜ」
「……うん、でもええわ。ここからでも充分見えるし」
城の方を向いているルビィの部屋の窓からは、屋根に邪魔されながらも赤青黄と、色とりどりの花火が何とか見えた。
「あんまり見えねぇじゃん」
と、ブランクも窓から空を見上げる。
「ええの、ここで」
ルビィは目を細めて微笑んだ。
夜空を映したようなブルーグレーの瞳に、光が模様を描く。
模様は火薬のはじける音と共に刻一刻と変化する―――まるで万華鏡のように。
ブランクは、じっとその横顔を見つめていた。
自分は何を恐れているのか。
彼女は何を恐れているのか。
踏み込んではならないと思っていた場所は、本当は踏み込まねばならない場所だったのかも知れない。
傷つけることを恐れて一歩も進まないことこそが、彼女を傷つける刃だったのでは?
「あ、ほら! 見てや、ブランク。綺麗やね〜!」
と、ルビィは空を指さし、ブランクの方を振り向いた。
刹那、花火を映していた瞳は、褐色の瞳を捕らえたまま、止まった。
夜空を指していた手をゆっくり降ろし、ルビィは二度だけ瞬きした。
自分を見つめる優しい瞳を、彼女はじっと覗き込んだ。
「……何?」
ごく密やかに、彼女は尋ねた。
返答の代わりに、頬にぬくもりを感じる。
そっと触れた、暖かい手。
「ブランク……?」
大音量で鳴り響いているはずの、花火の音が聞こえない。
代わりに、心臓の音が煩いくらい体中を占拠している。
ルビィは微かに震えた。
「怖いか?」
小さな問いかけに、不意に大きな愛情を感じて。
ルビィは否定の言葉を口にする代わりに、瞼を閉じて答えた。
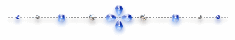
夜空に響き続ける花火の音。
耳には、ただその音だけが轟いていた。
ただ、ただ、その音だけが華やかに夜の闇を彩って。
ルビィは、閉じた瞼の裏に光を見た気がした。
|  BACK
BACK  NEXT
NEXT  Novels
Novels  TOP
TOP