|
彼女が初めて彼に笑顔を見せたのは、奇しくも彼があまり好もしく思わない自分の過去を話して聞かせた時だった。
翡翠色の瞳は真っ直ぐで直向だったけれど、いつも得体の知れぬ哀しみを抱えていた。
それが、気に障った。
強者が勝ち、弱者は生きる道を残されない。そんな世界に生きてきた彼には、斬れるように強い眼差しの奥に震えるような弱さを備えたあの目は、とても信じられない存在だった。
「男」と、彼女は言った。
「昔そう言った男がいた」―――と。
その「男」は、恋人である彼女のことはおろか、何もかもを忘れていた。
にもかかわらず、「男」は彼女の翠瞳の光を全て手中に収めた。
そして今、あの日の笑顔とは比べ物にならないほど、彼女は輝かしく、眩いばかりに微笑んでいた。
数え切れないほど堕ちた涙は全て土に還り、今ではもう、花を咲かせる糧となっただけなのかも知れない。
例えそうだとしても、彼の心に鈍い痛みを残すには充分な影だった。
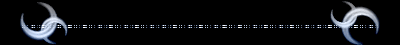
「あんたがそんなにお人好しだっただなんてね。てっきり、式場から花嫁を連れ去るもんだとばかり思ってたのに」
黒い瞳にからかうような色を浮かべ、ラニは言った。
「―――馬鹿か」
小さく吐息の混じった声色。
「何? あの人の幸せを願って泣く泣く身を引きます、ってわけ? 面白〜い、ダンナにそんなこと思わせるなんて、あの竜騎士さん」
「……黙れ」
「あのさぁ、ダンナ。一つ、言っておくけど」
ラニは顔を上げ、サラマンダーが咥えていたタバコを奪うと、一息、ふぅと煙を吐いた。
小麦色の肌に、黒い瞳はガラス細工のように光る。
旧知の女賞金稼ぎは、驚くほど精巧に彼の心を読んだ。
しかし、そんなことでうろたえる彼でもなかったし、もし彼がうろたえでもしたら、彼女の方が困ったに違いないのだった。
裏稼業NO.1と言われた男の、そんな素振りを見たくない、と。
「私の経験だけどね。人っていうのは、自分と同じ種類の人間に魅かれるもんなのよ。あの人は騎士だから、同じように真っ当な道を行く人が好みなわけ。ダンナとじゃ、生きてる世界が違いすぎる」
それがどうした、と、サラマンダーは内心思う。あの戦いでは、肩を並べ、この星を守るため共に戦ったのだ。
しかし、表に出たのは「ふん」という鼻息のみだった。
「ねぇ、ダンナ」
ラニはサラマンダーの様子に少し笑って見せてから、徐に逞しい肩口に頭を預けた。
「裏の道で思い出したけど、あの噂、本当だと思う?」
「噂?」
サラマンダーは不機嫌そうな声で聞き返した。
「トレノの街を騒がす闇の賞金稼ぎ」
その噂に覚えのないサラマンダーは、ややあってから、
「……お前か」
と呟く。ラニは「まさか」と声を立てて笑った。
「今更。賞金稼ぎなんてもうしないわ」
もしまだ続けてるなら、と、ラニは体を起こした。
「お楽しみの最中に、とっくにあんたの首を掻いてたわよ」
「おっかねぇな」
サラマンダーは鼻で哂った。
「もう足は洗ったの」
ラニはまた定位置に戻ると、そう囁いた。どことなく、寂しげな口調で。
一度その汚道に踏み込んだ足を、いくら洗っても綺麗にならないことは彼女も自分もわかっているから。
あの光は、眩し過ぎる。
| 
