|
〜十二夜〜
※十二夜・・・クリスマスから数えて十二日目の夜。一月六日の夜。
「全員集まったか〜? ほら、座れジェフリー」
ごつん、といい音がして、ジェフリーは自分の後頭部を右手で押さえた。
恨みがましい涙目で振り返った息子を無視し、ブランクは机の上に積んだ台本の山を、ポンポンと叩く。
「今度の舞台の配役を発表するぞ」
年の初めにあったアレクサンドリア公演の余韻もまだ抜けぬ、春。
タンタラス劇団は新しい舞台の準備に入っていた。
いくつかあった演目の候補から最終的に絞られたのは、エイヴォン卿の作品『十二夜』。
エイヴォン卿の作品には珍しく、喜劇だ。
「公爵、ラリ。セバスチャン、ジェフリー。道化、ハリー。オリヴィア、リアナ」
配役を発表しながら、一人一人に台本を手渡していく。
最後に残った少女が、青い目を不安げに揺らした。
「ヴァイオラ、サフィー」
「あたし……?」
「ああ、そうだ」
彼女はうろたえて、リアナを見た。
てっきり、主役はリアナに違いないと思っていたのに。
「あたしには、まだ無理だわ」
サファイアは小さく呟いた。
***
演目自体は二週間も前に発表されていたので、既に原本には何度か目を通していた。
が、実際には役者の数の問題もあり、台本では台詞回しや話の展開が多少変わることもある。
ミーティングがお開きになると、サファイアはブランクに呼ばれて、楽譜を手渡された。
「これ、二幕で使う歌だから」
「あたしが歌うの?」
ブランクはにっこり微笑むと、頷いた。
「ハリーはあと二曲歌うし、ここはサフィーが歌った方がいいだろう」
歌は、嫌いじゃない。
でも、でたらめな鼻歌と、舞台の上で歌うのとでは大違いだ。
「おじさ……じゃなくて、ボス」
「ん?」
正式にタンタラスのメンバーに加えられてから、サファイアはブランクを「ボス」、ルビィを「おかみさん」と呼ぶようにしていた。
いまだに慣れない呼び方で、呼ぶ方も呼ばれる方も戸惑うのだが。
「あたし、自信がないわ」
「そりゃ、誰でも初めはそうだ」
ヴァイオラは、リアナが適役だ。
そう思っても、団長に意見を言える身分でないことも彼女はわかっていた。
「しっかり練習すれば、大丈夫だよ」
ブランクはサファイアの短い金髪を撫でた。それで、サファイアはもう何も言えなくなる。
仕草が父とよく似ていて、いつも少し切なくなった。
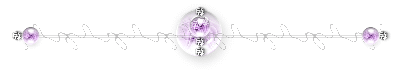
「サフィーさん、まだ起きてたんっスか?」
ランプを片手に居間へ降りてきたハリーは、気遣わしげな声を掛けた。
サファイアは食卓で台本を読んでいた。
「寒くないっスか?」
「大丈夫」
と、曖昧に微笑む。
「そんなに根詰めても仕方ないっスよ」
隣の椅子を引いて、ハリーは腰掛けた。
「だって……」
サファイアは口ごもって俯いた。
ランプの仄かな明かりが彼女の横顔を照らし、太陽のように元気な少女の、月のような一面を映し出す。
やっぱり似てるな、とハリーは思った。
普段は誰にも見せない、影のようなその一瞬が彼は好きだった。
「読み合わせ、するっスか?」
「……え?」
「一緒のシーンは多くないっスけど、きっと気分が落ち着くっス」
顔を上げて目を丸くするサファイアに、ハリーはその辺に放ってあった台本を手に取って示した。
「三幕の第一場面っス」
サファイアは慌ててページを捲った。
***
ヴァイオラ:「こんにちは。(道化が腰にぶら下げた小太鼓を見て)君は太鼓で暮らしてるの?」
道化:「いいえ、旦那。あっしは教会で暮らしてるんでさ」
ヴァイオラ:「じゃぁ、僧侶なのかい?」
道化:「いやいや、あっしは教会の側に住んでいるわけで、つまりは自分の家に住んではいるが、家は教会の側に建ってるってわけです」
ヴァイオラ:「君はオリヴィア嬢の道化師ではないのかい?」
道化:「実は違いますんで、旦那。オリヴィア譲は結婚するまで道化は囲わないでしょうさ。まぁ、夫と道化はイワシとニシンみたい瓜二つってなもんでさ。あっしはあの方の道化じゃありやせんが、言葉の賄賂をお贈りしてるんで」
ヴァイオラ:「オーシーノ伯爵のところで会ったね」
道化:「気の毒にもこの道化は、かかあといるようにあんたのご主人のところにいなきゃぁならんわけでして。それでもって、あっしは旦那の知恵を拝見したわけですな」
ヴァイオラ:「僕のせいにしないでおくれよ。さぁ、お駄賃だ」
道化:「ああ、神様! ちょいとこの人に顎髭をやっておくれまし」
ヴァイオラ:「本当を言うと、そのことでは悩んでるんだ――(心の中で)自分の顎に髭が生えて欲しいってことではないけれど――お嬢様はご在宅で?」
道化:「おられますですよ、旦那。あなたがおいでになったって事をお伝えしてきましょう」
  
|