|
アレクサンドリア城の客間は、特に数が多い。
議会の度に遠方から遥々足を伸ばす貴族たちが期間中の宿とするため、この城にはあらゆる大きさやあらゆる調度の客間がずらりと並んでいる。
階が上がるほど豪華な部屋になり、それぞれ掃除する女中衆の顔ぶれさえも違うらしい。
だから、客室区最下層にある客間は全て、どんな時も使われることはない。
一番下の客室を充てられたとあっては、客人が憤慨するだろうからだ。
古くからの伝統を守り、ガーネット女王は誰にも最下層の部屋を使わせなかった。
そう。ただ一人、その人物を除いては―――。
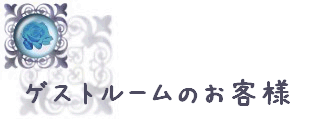
<1>
ガーネットは客室区の階段を軽やかな足取りで降りていた。
午前中の仕事が一つキャンセルになり、不意の休息をもらったのだ。
誰も使わない階とは言え、灯りが絶えることも掃除を怠ることもないので、女王である彼女が使う居住区より、この辺りはずっと美しい様相だった。
ガーネットは小さくハミングしながら、踊るように廊下へ降り立った。
そして、すぐ右手の扉を、行儀正しい彼女らしくもなく、ノックもせずに開けた。
扉はいつも通り、鍵さえ掛かっていなかった。
そっと中を覗くと、まるで誰もいないかのような静けさ。
ガーネットは足音を忍ばせて寝台へ歩み寄る。
彼女が会いたくてたまらなかった青年は、そこでぐっすりと眠っていた。
あまりにぐっすり眠っているので、まるでぴくりとも動かないようだった。
彼は、いつもそんな風に静かに眠った。
最初の頃、ガーネットは死んでしまったのではないかと不安になり、耳を近付けて寝息を確かめたほどだった。
あの旅の途中では、こんな風に眠っているなんて全く気付かなかった。
それだけ、自分のことで精一杯だったのだろう。
彼女が覚えているのは、猫のように丸まって寝ている彼の後姿だけだった。いつもテントの隅っこで、みんなに背を向けて丸くなっていた。
でも、そんな風に眠るのは彼だけじゃなかった。
サラマンダーも、フライヤも、一人孤独と戦う人はみなそんな風に眠った。
だから、きっと。
彼もまた、孤独だったのだ。
夏の爽やかな朝で、大きな窓からは燦燦と太陽が降り注いでいた。
彼女は微笑みながら、静かに寝台へ腰を下ろした。
彼が死んでしまったのではないかと不安になるのは、この眠り方のせいだけではなかった。
彼が無事に彼女の元へ辿り着いてからも、彼女の心の奥底に住み着いてしまった不安は、そう簡単に消え去ってはくれなかったのだ。
だから、彼女は時々、思い出したようにひどく不安になった。
そしてその度に、彼は静かに彼女を抱き締めた。
―――彼女の心から、闇が引いてゆくまで、ずっと。
彼のそんな暖かさが、彼女には嬉しかった。
夢ではない現実なのだと、いつも感じさせてくれたから。
ジタンは半ば布団に埋もれたまま、くぅくぅと小さな寝息を立てて寝こけている。
この御仁、朝寝坊が酷い。
あまりに酷いので、もう誰も起こしに来なくなった。
それでも以前は、この階の担当の女中衆の誰かが――彼女たちの多くはガーネットと同じような年頃だった――、朝ご飯の時間だとか、そろそろ掃除の時間だとか、一生懸命起こそうとしていたのだが。
結局、ノックもせずに勝手に部屋に入れるのは女王だけだった。
だから、時間があれば彼女が起こしに来るか、来なければ最悪昼ごろまで寝ているのだ。
「ジタン」
ガーネットは静かに呼んでみる。
これくらいでは絶対起きない。
……いい夢でも見ているのか、口元が緩んでいる。
「ジタンったら」
少しだけ、瞼が震えた、が。
まだぐぅぐぅ寝入っている。
ガーネットは右手の親指と人差し指で、彼の鼻を思い切り抓まんだ。
「ジ・タ・ン! 起きなさいってば!」
「ふがっ?」
尻尾の毛を文字通り逆立てて、ジタンはガバッと跳ね起きた。自分の置かれている状況が掴めないのか、寝惚けた頭で必死に考えているらしいのが可笑しくて、ガーネットは小さく笑いを洩らした。
「はんへ、らがーがほほひひるんら?」
「何ですって?」
ガーネットは抓んだままだったジタンの鼻を解放した。
「だから、なんでダガーがここにいるのかって聞いたんだよ」
「あら、いたらいけない?」
ガーネットが嘯くと、ジタンはバサッと毛布を剥いで身を乗り出した。
「そんなこと言ってないだろ!」
あんまり必死に言うので、ガーネットは可笑しくてまた笑った。
「兎に角、先に顔を洗って来たら? 頭もどうなっちゃってるの、寝癖だらけよ」
ガーネットがそう言うと、ジタンははっとしてベッドから飛び起きた。
「不意討ちだろー!」
言われた通りに顔を洗い、髪を撫で付け、服を着替えると、ガーネットが座っているテーブルの向かい側に座った。
「仕事は?」
「午前中は休みになったの」
その途端、ジタンの目が微かにキラリと光った。それで、ガーネットはわざと意地悪なことを言いたくなった。
「だから、あなたが朝ご飯を食べている間、お茶を飲みながらそれを監視することもできるし、あなたが脱ぎ散らかしたパジャマと起き抜けたままのベッドを直すのも監視できるし、可愛いメイドを口説いたりしないように監視もできるのよ」
「……最後のは余計だし」
ジタンは運ばれてきたトーストと目玉焼きとサラダを食べ始め、ガーネットは向かいの席で紅茶を飲んで、二人は色々なことを話した。
エーコのリンドブルムでの暮らしぶり。スタイナーとベアトリクスの結婚式の話。フラットレイとフライヤの話。
「サラマンダー、あれからどうしてるか知ってるか?」
「トレノに住んでるって聞いたけど、詳しいことは知らないわ」
ガーネットはそう答えた。
サラマンダーはちょくちょく手紙を書いてくるような性質ではないし、近況報告は人伝に聞くだけだった。
「でも、トレノで何か揉め事があったら私のところに知らせが来るんだから、便りがないのは元気な証拠よ」
「そうだな」
ジタンはニッと笑って頷いた。実際、サラマンダーから手紙が来たら、何事かとみんな慌てるに違いないと思った。
「タンタラスの人たちは元気かしら」
「どうだろうなー、ルビィが言うには変わりないって話だけど」
「ルビィさん、最近こっちに詰めっぱなしなの?」
「みたいだな」
小劇場で出し物がある時は、ルビィはアレクサンドリアに長期滞在していた。今回はもう三月もいることになる。
「なんて言うかあいつら、擦れ違ってるって言うか、あと一歩が足りないって言うかさ」
ジタンがぼやくと、ガーネットは悪戯っぽい目をして彼を見た。ジタンが誰のことを言っているのか、一目瞭然だった。
「ミコトから手紙が来てたわ」
ガーネットは懐から封筒を取り出した。
「オレには全然書いてくんないもんなー」
ジタンは唇を尖らせた。
「ビビの子供たちも、他のみんなも元気ですって。小物のお店は繁盛してるそうよ」
「ふーん」
ジタンはサラダのトマトを突っつき回しながら、幾分気のない相槌をした。
「ジタン、そんな風にしたらお行儀が悪いわ」
「いいじゃん、ダガーしかいないんだし」
種の部分を取ってしまうと、ジタンは残りをポイッと口に放り込んだ。
「好き嫌いしないの」
ガーネットが更に注意すると、ジタンはちぇ、と小さく呟いて、さっき取り除いた部分も口に入れた。
|  NEXT
NEXT  Novels
Novels  TOP
TOP
 NEXT
NEXT  Novels
Novels  TOP
TOP