アレクサンドリアに降り立ったジタンは、街の中ですごいものを見てしまった。
一瞬ぎょっとした彼は、あまりに唖然として言葉も出なかった。
なんと、ガーネットに贈ったあの指輪と、同じ指輪をしている少女がいたのだ。
それも、一人や二人の話ではなかった……!
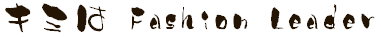
「で、流行っちゃったってわけか」
ジタンは苦笑した。
その指輪は、以前ジタンがガーネットの誕生日に贈ったもので、サファイアとガーネットの小ぶりな石が入った指輪だった。
リンドブルムの宝飾職人から買ったもので、同じデザインの指輪はこの世に二つとないはずだったのだ。
彼の恋人はひどく申し訳なさそうに首を竦めていた。
「ごめんなさい……」
その様子がなんだか可笑しくて可愛くて、青い目はすこぶるご機嫌だった。
「ダガーが悪いんじゃないだろ? 不可抗力ってやつさ」
ガーネットは頬を染めたまま、答えに困って蹲っていた。
公務に、あの指輪をつけて行った。
それはガーネットなりの決意表明だった。
そこに至るまで、ガーネットは色々なことを思い惑った。
騒ぎになっては困ると思った。彼に迷惑を掛けるわけにはいかないとも思った。
それでも、自分の心が彼の許にあるのだということを知らしめたいという気持ちが、どんどんと膨らんでいくのを止められなかったのだ。
だから、指輪をつけて行った。
案の定、『女王の指輪』は様々な憶測を呼んだ。
恋人? 婚約者?
ついに結婚か?
未婚の女性が左の薬指に指輪などはしたない、という声が聞こえてきた時にはほんの少しだけ落ち込んだけれど、ガーネットは決して指輪を外さなかった。
これはわたしの決意なのだ。彼への誠意なのだ。
あなたの想いを、一番側で感じていたいから。
やがて、彼女の思いも寄らない事態が訪れた。
アレクサンドリアで、若い女性に流行ってしまったのだ―――あの、赤と青の石が入った指輪のデザインが。
いまやアレクサンドリアのアクセサリー屋というアクセサリー屋はみな、あのデザインの指輪(もちろんイミテーションではあったが)を扱っていた。
『話題の人気商品! 女王陛下の指輪と同じデザインです!!』
……どの店も売り切れ続出らしい。
そのことを知ったガーネットはあまりにびっくりしてオロオロしたが、どうにもならなかった。
まさか、「そのデザインを使ってはいけません」なんて女王命令はできなかった。そんなことをしたら職権乱用だ。
かくして、アレクサンドリアで大流行となった指輪は変わらず女王の指に輝いていたが、その主はすっかり意気消沈していたのだった。
ベアトリクスとスタイナーが、トットの力も借りて知恵を絞り、「偽造にあたるため法律違反である」として指輪の回収に走り始めたのは、そんな騒ぎが大きくなってから二月ほど後のことだった。
それに対抗したのが、若い少女たちである。
憧れの女王陛下と同じ指輪をする。これが若い彼女たちにとってのステータスとなっていたのだ。
ベアトリクス隊とプルート隊が東奔西走したが、指輪はその目を盗んで作られ、少女たちに買われていった。
街は、赤と青の石の指輪で溢れていた。今更その火を揉み消すことなどできそうもなかった。
そして、今に至るのである。
「どうしようもないの……どうにかしたいとは思うんだけど」
ガーネットは消え入りそうな声で言い訳した。
「ジタンが見たらびっくりするだろうと思って」
「うん、びっくりした」
ジタンは素直に頷いて笑った。
「しかし、みんなよく見てるんだなぁ」
白くて細い指にそっと触れる。相変わらず、あの指輪はそこに居た。どこか誇らしげに、どこかひっそりと―――それは、まるで彼女の心を表してでもいるかのようだった。
「なんか、嬉しいな」
ジタンはそう呟いた。
「え?」
聞きとがめたガーネットが目を見開いた。
「みんなが真似したことが?」
まさか、とジタンは噴き出したが、ガーネットがあまりに真面目な顔で訊くので、おどけて見せただけだった。
でも、とガーネットは言う。
「どうしたらいいのかしら、本当に。あなたに貰った物に変わりはないのに、何だかおかしな気持ちなの」
「うーん」
ジタンは後頭を掻いた。
「じゃぁ、その指輪はやめる?」
「嫌よ!」
ガーネットは即座に強く否定した。
あまりに勢い付いて言うので、ジタンは軽く体を仰け反らせたくらいだった。
「まぁ、そのうちみんな飽きるだろ」
「それも……何だかイヤ」
「なんで」
ジタンは笑った。
ガーネットは、大事そうに自分の左手を胸に抱き締めている。
「だって、この指輪が飽きられるなんて、何だかイヤなんだもの」
「ふーん」
気付けば、ジタンはニヤニヤとガーネットを見ていた。
「……!」
あっという間に頬が真っ赤に染まり、ガーネットはやけくそでジタンの背中を叩いた。
「もう、ジタンのバカ!」
***
ジタンのバカ、と言ってはみたものの、もちろんそんなことで事態が解決するはずもなく。
ガーネットはほとほと困り果てていた。
なぜかあの指輪の件以来、ガーネットの身につけるものが流行るようになってしまったのだ。
ガーネットが何気なく首に巻いていたスカーフは、「ガーネット巻き」として少女たちに真似され、何気なく結った髪型が「ガーネット結い」として持てはやされた。
ガーネットがフレアのふわりとしたスカートをはいたと耳にすれば、「ガーネットライン」なるスカートが流行った。
それだけの騒ぎになれば、廊下ですれ違った老齢の大臣にさえ、「今日のお召し物はどのようなものですかな?」などと尋ねられる始末だった。
みんなに見られていると思うとぞんざいな格好もできず、ガーネットは朝一番から、センスの良い女中に「今日の服装」を相談するようになったほどだった。
「城下町で流行っておりますよ、こちらのコートは」
と、ベアトリクスがガーネットに伝えた。
寒くなってきたので、行幸にと新調したコートを羽織ったのだが、早速そのデザインがアレクサンドリアのファッションに取り入れられたらしい。
トレンチ型のコートで、どことなく女性らしいデザイン。
「いつの間にそういう風になっちゃったのかしら」
ガーネットは困惑した顔で言った。
「ガーネット様は若い女性たちの憧れの的ですから、不思議なことは何もございませんよ」
と言うベアトリクスも、いわゆる「ガーネット巻き」である。
「でも、みんなに監視されているみたいで、居心地が悪いわ」
ガーネットは無意識に左手の指輪を撫でた。
ああ、そうだ。ここから始まったのだ。
ジタンがセンスのいい指輪をくれるから、こういうことになったんだわ。
ときに、その「センスのいい」ジタンは、最近とんとご無沙汰だった。
「仕事が忙しくて」
と、らしくもない理由を述べたジタン。
「トレジャーハンティング?」
「いや、ボスが新しい商売を始めてさ。それを手伝ってるんだ」
どんな商売なのかは聞かなかった。また、ラッキーカラー商会のような怪しげな商売をしているのだろうか。
ジタンは本当に忙しいらしく、滅多にアレクサンドリアを訪れなかった。
―――もしかして、怒ったのかしら。
ガーネットはある時そう思いついて、酷く哀しい気持ちになった。
ジタンにとっても特別だったはずの指輪。それがみんなに真似されたとあれば、怒ってしまって当たり前だ。
ガーネットの思いとは裏腹に、彼女の身につける服やら小物やらは大流行であった。
今は「ガーネットヒール」と呼ばれる、ヒールの細い靴が流行っている。
***
「ジタン!」
何ヶ月かぶりに、ジタンがアレクサンドリアを訪れた。
ガーネットがいつにないほど歓迎してくれるので、ジタンもいつも以上の笑顔になる。
「どうしてなかなか来てくれなかったの?」
「ごめんな、ホントに忙しくてさ」
「……そうなの」
やっぱり怒っていたのだろうか。しかし、ジタンはニコニコしていて、怒っているとは考え難かった。
「ジタンが来ない間も、大変だったのよ」
「ああ、聞いた聞いた。『ガーネットネイル』に『ガーネット編みニット』だっけ?」
ガーネットは困ったように頷いた。
「そういうのって、リンドブルムではファッション・リーダーっていうんだぜ」
「リーダー?」
「そう。人気女優の着た服が流行ったりしてさ。どこも同じだな」
ジタンは笑った。
「まぁ、女王のファッションが流行るっていうのは、なかなか珍しいことかもしれないけど。人気者のしるしってことだよ」
そんな風に言われたら嬉しくなくもなかったが、ガーネットは複雑そうな顔でジタンを見ていた。
しかし、ジタンがいれば楽しくて、そんな憂い事は頭の片隅に追いやられた。ジタンはいつも以上に饒舌で、ここ数ヶ月にリンドブルムで起きた滑稽な出来事を面白おかしく話してくれた。
そうこうしているうちに夜が更け、月が夜空の真上に差し掛かった頃、不意に二人はぴたりと話を止めた。
正確には、ジタンが喋るのを止めたのだ。
ガーネットは少し驚いて、ジタンの顔を覗き込んだ。
「ダガー」
ジタンは今までとは打って変わって、真剣な声を出した。
「なぁに?」
ガーネットも、今まで散々笑い転げていたのが嘘のように、静かな声で答えた。
しかし、ジタンはまた黙り込んでしまった。
ガーネットは何事かと小首を傾げる。
やがて、ジタンは決心したように、ポケットに突っ込んでいた右手を出した。そして、物も言わず、ガーネットの左手の薬指からあの指輪を抜いた。
「ジ、ジタン?!」
やっぱり怒っていたんだ。ガーネットは確信した。
彼との関係がこんな風に終わってしまうのは嫌だった。けれど、こればかりはどうすることもできなかった。女王という職業柄、嫌でも人前に出なければならず、結果、嫌でも流行の中心に鎮座せねばならなかった。ガーネットは困惑し続けたが、こればかりはどうすることもできなかったのだ―――!
今しもガーネットが泣き出そうとした時、ジタンの右手は抜き去った指輪を側のテーブルに置き、再び彼のズボンのポケットに納まった。そして、次に出てきた時には何かを握り締めていた。
「ダガー」
もう一度名を呼ぶと、ジタンは再びガーネットの指に指輪を填めた。あの、可愛らしいデザインの指輪とは違う、とてもシンプルなそれ。
ガーネットはまじまじと自分の指を見つめた。
「結婚しよう」
緊張した声がそう言った時、ついにガーネットはパニックになった。
目を丸くして自分を見つめるガーネットに、ジタンは繰り返し告げた。
「オレと結婚してください」
ガーネットは数度瞬きした。なかなか声が出ない。
「ダガー?」
「あ、あの……」
やっとガーネットの思考回路が作動し始めたらしい、と思った次の瞬間。
ジタンは、我が耳を疑った。
「か、考えさせてください……」
消え入りそうな声で、ガーネットはそう言った。
***
ガーネットはベッドでさめざめと泣いていた。
あの後、ジタンは挨拶もそこそこに帰ってしまった。きっと酷くショックを受けたのだろう。
どうして「考えさせて」なんて言ってしまったのだろう。ガーネットは後悔して泣いていた。
どうしてなのか、自分でもわからなかった。確かに気は動転していた。「結婚」なんてまだまだ先の話だと思っていたし、心の準備など全くなかった。
ジタンは指輪のことで怒っているのだとばかり思っていたから、まさかいきなりプロポーズされるなんて考えも及ばなかったのだ。
でも、どんなに急なことだって、ジタンを愛しているし、いつかは結婚するのだと思っていたのだから、どうしてYESと言えなかったのか、ガーネットはわからなくて泣き続けた。
きっと、一瞬国のことが頭をよぎったのだろうとガーネットは考えた。
自由にはならない自分の身を思えば、いくらプライベートとは言え、その場でYESとは言い難かったのだろうと。
そう思えば、自分は彼のことを何だと思っていたのかと、ガーネットはますます泣いた。
泣きすぎて翌日目が腫れ、それを隠すために淡く色のついた眼鏡を掛けていたら、それが流行って「ガーネットカラーグラス」となった。
***
しばらくの間、ジタンの足はアレクサンドリアから遠のいていた。
ジタンが来ない間、ずっと落ち込んだままだったガーネット。どうしたことかと周りの人間たちが見るに見兼ねるほどだった。
やがてジタンが再びアレクサンドリアへやって来たので、密かに側近たちはほっとしたが、ガーネットは喜んでいるというより、慌てているように見えた。
ジタンの姿を認めるやいなや、ガーネットは立ち上がって口を開いた。
「あの、ジタン。わたし……」
言わなければ。YESと言わなければ。そして謝らなければ。
ガーネットはジタンに会わなかった間に心の中で何度も繰り返したその言葉を、声に出そうと息を吸い込んだ。しかし。
「ごめんな、ダガー」
開口一番、ジタンの方があっさりと謝罪を口にした。
「やっぱり、いくらなんでもいきなり過ぎたよな」
そう言って、彼は頭を掻いた。
「ダガーの心が決まるまで、のんびり待ってるからさ」
何か言おうと口を開いたガーネットが言葉を発する前に、
「ごめんな」
ジタンは寂しそうにそう言った。
そんな声で謝られたら、ガーネットはもう何も言えなくなってしまう。
そうしてガーネットは自分の気持ちを伝える機会を失い、結局それでプロポーズの件はなかったことになった。
その日も相変わらずジタンは饒舌だったが、ガーネットは気がそぞろで、彼の話を半分も聞いていなかった。時々、ぼんやりしている自分に気付いて意識を戻そう、彼の話に注意を払おうとしたが、なかなか上手くいかなかった。
ジタンは心なしかしょんぼりして帰っていった。その後姿を見送りながら、ガーネットは色々なことを考えていた。
そして、彼女は決心した。
***
アレクサンドリアに降り立ったジタンは、ぎょっとして立ち止まった。
なんと、ガーネットに贈ったあの指輪と、同じ指輪をしている少女がいたのだ。
しかも、一人や二人の話ではなかった。
気付けば、アレクサンドリアのアクセサリー屋というアクセサリー屋には、こんな触れ込みでその指輪が置かれていた。
『カップルにオススメ! 女王陛下の婚約指輪と同じデザインです!!』
「ダガー!」
庭先にいたガーネットを見つけ、ジタンが駆け寄って抱き締めたのは、1月15日の寒い午後のことだった。
-Fin-
姫、今年もお誕生日おめでとう! 今年も無事にお祝いすることができて、とても嬉しいです。
今年はついに、この二人も結婚までこぎつけてくれました(笑)
なんだか安いファッションが流行ってしまいましたが、決して姫のせいではなく、
ひとえに作者にセンスがないだけの話です・・・(^^;)
何はともあれ、姫におめでとうと、そして主催者のリュートさんに心からありがとうと言いたいです!
2006.1.15 せい
Birthmoon TOP
|